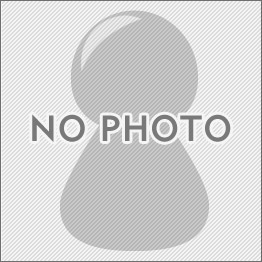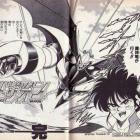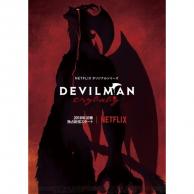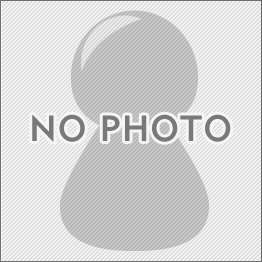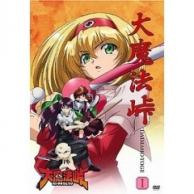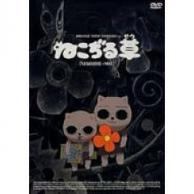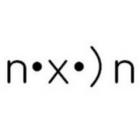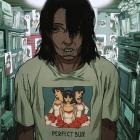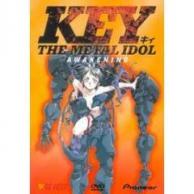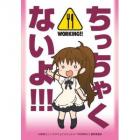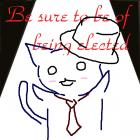ほーきんす♪ さんの感想・評価
3.6
【ネタバレ有】 『ちょうどいいさじ加減の「グロホラー作品」!』
アニメを観る前に、原作が何であるかや、どういった作品なのかは全く知らない、フラットな状態でアニメを観るように心がけているので、この作品も↑の画像のみの情報しかなかった…。
そのため、観る前は、生徒たちが殺し合いをする、いわゆる「バトロワ(バトル・ロワイアル)」的要素の作品かと思っていた。
しかし、実際は、閉鎖空間に閉じ込められた人たちが、霊によって無差別に殺される、(グロ)ホラー作品だった。
これは、観た人それぞれがどう感じるかであるから、あまり口をはさむことではないかもしれないが…、このレビュー自体、個人的なものであるのだから書かせてもらう…。
この手のアニメ作品は、“アニメ作品”であるがゆえに、どうしても作画をリアルすぎる描写にすることができず、作画のみで“グロい”と思うことは難しい…(例えば、“子供たちが縛られて、生きたまま舌を切られる”シーンなどは誰がどう考えてもグロいが、それは作画ではなく、話の展開や設定などの一連の流れによるグロさである)。
なので、この作品のグロシーン(の画だけ)を観て、本当にグロかった、怖かったなどと思うような人は、良い意味では想像力豊かな人、悪く言うなら(現実においても)ぬるい甘ちゃん性質な人だと思う…(グロ要素で言えば、ハリウッド映画の「テキサス・チェーンソー」シリーズ、ホラー要素で言えば、「グレイヴ・エンカウンターズ」(ちなみに、ホラー映画マニアにまでなると、この作品を低評価する人たちをたまに見かけるが、そういう人たちは、売れた映画ではなく、マニアックな作品をつこうとする傾向がある…)などは、まともに観ることさえ出来ないだろう…)。
まぁ、そんなことはさておき、この作品を他の作品と比べての純粋な評価をするなら、上記の“グロ要素”、“ホラー要素”、“話の展開”やホラー作品ならではの“落ち”など、どれをとっても「Another」の劣化版であった。
「Another」は、視聴者が「どういう設定何だろう?」などと、その後の展開などを予想し、それが裏切られる、またその裏切られるタイミングで今までのかんじとは一気に180度切り替わる、ことによって、視聴者に恐怖感を与えることに成功していた。
しかし、この作品にはそれがなく、キャラが振り返ったところに、急に霊の顔がある…などの怖さ(お化け屋敷的な怖がらせ方)しかなかった。
(おそらくだが、)この作品の原作はコンピュータゲームであるが故に、ただ単にプレーヤーに恐怖感を与えるというのではなく、いろいろと情報を集めたり、進んでいくうちに物語が展開していく、RPG的要素を含んだ作品にしたのではないだろうか…。
そのためか、アニメ作品内にも、“さっきまで開かなかったページが、ある出来事の後には開くことができる”など、ゲーム的要素をかんじるシーンがたびたびあった。
少し批判が過ぎるようなレビューになってしまったので、良かったところをあげると、最後の生き残った3人が、元の世界に帰るためにおまじないをするシーンがあったが、あれはかなり怖かった…。
というのも…、サトシだけが帰って来れず、サトシの腕だけが元の世界に帰って来たことに恐怖を感じたのではない。
展開を予想しながら観ている人からすれば分かっていたと思うが、ナオミが紙(の切れ端)を無くしたそぶりを見せるあたりから(もっと言うなら、セイコが最初に「その紙トイレで無くしてしまったみたい」的なことを言うあたりから)、その切れ端が自分のである(実際は、一緒に来た人のならどれでもよい)ことに意味があって、そうでない場合は帰ることが出来ない、ということはおおかた予想できていた。
なので、サトシが帰れなかったことに恐怖を感じたのではなく、(ここからはただの想像である…)もしサトシが、“自分たち以外の切れ端を使った場合死ぬ”ということを予想していて、それでもなお、一緒に “帰るおまじない”を続けた、のであれば…、最愛の妹がいない元の世界など生きている価値などなく、自分もはじめから死ぬ気でいたのではないか…(おまじないをするかなり前から、サトシは霊の女の子に“自分達の切れ端以外を使った場合”のことを聞いている…)。
もしそうだと考えるなら、ナオミ達に「俺はユカのがあるから大丈夫」などと笑顔で言っておきながら、ユカと同じ世界(=天国)に行こうとしていたことになり、ある意味では、モリシゲと同じように、すでに“壊れていた”のではないだろうか…、と考えてしまう(ちなみに、そのせい(自分の切れ端が他人のであり、おそらくは自分は戻れないだろうとナオミ達に言わなかったこと)でナオミは、腕だけのサトシを見て、結果的に“壊れてしまう”)。
と、まぁ、ここまで深く考えてみたらかなり怖い作品だったなとも感じる(…が、あくまでこれは個人的な妄想である)。
(それと改めて考えてみると、自分のために命を懸けて戻ってきたキシヌマに対するシノザキの反応や、立ち直りの早さにはある意味恐怖した…。)
(あと余談だが…)ナオミの声が「佐藤利奈」、セイコの声が「新井里美」(ここまで言えば分かる人には分かるだろうが…)であったせいで、ちょっとしたことに恐怖を感じたり、セイコに当たったりするところが、御坂(とあるシリーズ)ならそんな(精神的に)弱くないだろ…と、考えてしまって、物語に入っていきにくかった(2人の関係も“とあるシリーズ”の関係に似ている…)。
よって、結論としては、あまりグロい系、ホラー系が得意でない人には、ちょうどいいさじ加減の“グロこわ作品”だったのではないだろうか…。
(終)