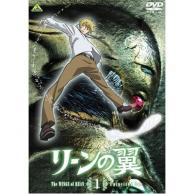ぺー さんの感想・評価
4.3
千代に八千代に千変万化
オリジナルアニメ劇場版
『東京ゴッドファーザーズ』に端を発しての今敏監督作品3本目の視聴。『PERFECT BLUE』を挟んで本作です。
氏の作品については、“虚構”と“現実”入り乱れる作風が特徴との交流あるレビュアーさんの言及があり、まさにその通りなんだろうと思います。
前作『PERFECT BLUE』でも、本作『千年女優』でも物語の主役は“女優”です。作り手が発信したいメッセージを表現するには、虚構を演じる職業柄“女優”という属性は語り部にふさわしいのかもしれません。
両作品とも現在進行形の今(現実)があって、そこに撮影シーンいわゆる劇中劇(虚構)が挿入されて次第に溶け合っていくのを基本構成としてました。
基本構成のみが前作とすれば、本作では女優藤原千代子の過去語り(回想)も加わることでより一層カオス度合いが増した印象。それでいて最後はきっちり収束するので観てて心地よかったです。
“女優”を扱った同氏の作品を続けて鑑賞したのはよい対比となりました。視聴順の推奨というほどでもありませんが、これからご覧なられる方は片隅にでも留意いただけるとよいかもです。
隠居した往年の名女優のインタビューをとりに女優宅を映像制作会社の社長さんが訪れるところから物語はスタート。
女優の名は藤原千代子。千代子の大ファンでもある社長さんは立花源也。千代子の半生を辿るドキュメンタリー製作が口実での訪問だったが、その半生がどういったものかもそしてインタビューを千代子が受けようとした理由も、鍵を握るのは立花が持参したあるおみやげでした、と。
以後、千代子が女優になったきっかけからの回想が始まり、出演映画のシーンも織り交ぜながら想い人である絵描きの青年を追いかけるストーリーが展開されていきます。はたして想いは成就されるのされないの?に視点を置いての鑑賞になるでしょう。
以下2点の両立がなされているところは高く評価したいです。
1.上っ面だけかすめても面白い
2.小難しく考えても面白い
どっちかに特化しても良いんですけどね。
1.上っ面だけかすめても面白い
映画の大半を占める千代子の半生語りの回想は、劇中劇と合わせて独特の空気を醸し出してます。普通は回想と現在との2本立てなところを、“回想”“劇中劇”“現在”3本立てで構成されているのは先述の通りです。それが溶け合ってチャンプルーしてるのが特徴となります。
複数場面が溶け合ってることのみならず、そこに登場するキャラにも捻りを加えてきます。過去の千代子、役を演じてる千代子、現在の千代子とその場面に合わせた登場人物たち。加えてインタビュアーたる立花と同行のアシスタントくんが回想と劇中劇にも顔を出してくるのです。なかなかお目にかかれない演出です。視聴者が??となりそうな箇所ではアシスタントくんが適度なツッコミを入れてくれるので置き去りにならない設計になってるとも思いました。
ここまででも新鮮味がある作品設計という強みがあるのですが、なによりテンポがよいのです。そして美しいのです。そんなお金かけてる気はしないんですが。。。
{netabare}馬賊に襲われているところからの戦国への転調シーンなど本来なら不自然なはずなのにカット割りが自然で気にならない。{/netabare}
{netabare}町娘が追いかけてる時の背景が浮世絵絵巻物風で、美しいと思える背景美術となっている。{/netabare}
{netabare}映画全盛期の昭和30年代。街並みから映画チラシ。家の中の家具調度品などの郷愁感。すなわち『三丁目の夕日』感っていうやつです。もしくは『新横浜ラーメン博物館』感のどちらでも。{/netabare}
{netabare}印象深いのは雪景色。絵描きの青年との出会い/別離のシーンであったり、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」的なシーンもありました。そのまんまでも綺麗なのですが、{netabare}絵描きの青年(役名は鍵の男)の郷土北海道の暗喩だったんでしょうね。{/netabare}{/netabare}
そもそもの話で、おばあちゃん千代子さんの佇まいの品の良さとたまに見せる少女のかわいらしさには触れておきたいかも。ヒロインへの感情移入の土台となるのは、往年の名女優の現在の立ち居振る舞いだったと感じます。
めくるめく場面展開の独創性が面白さの源泉であり、本流である想い人を追いかけるエモさは古今東西受け入れやすかろう物語でした。締めの一言がラブストーリーとして見立てた本作の評価に直結するくらいでしょうが、賛否両論あるくらいがこの作品にスパイスが利いていた証左です。
2.小難しく考えても面白い
やはり幕の降ろし方が気になります。
頭を使いそうな作品に遭遇した時、理解の手助けの一つとして冒頭シーンの意味をよく考えたりします。作品の開幕に監督がどのような意図をもって何を用意したかが表れているから、が理由。
その視点で本作を眺めた場合、※以下視聴済の方向けネタバレ
{netabare}千代子にとって想い人を追いかけることを止めて女優も引退したという人生の分岐点があの宇宙飛行士役の一幕でした。
“鍵”“地震”“老婆”“鍵の男”なにかしら示唆する暗喩めいたものは数多く配置されてるのが本作です。この宇宙飛行のシーンは冒頭と中間そしてラストと都合3回出てきますが、中間部分で二度目の鍵の紛失という事態に見舞われます。
一度目の紛失の際、千代子は結婚し家庭に入ってしまいます。劇中劇は「もう顔も思いだせない」と咽び泣いた教員役の1カットのみ。触れられてませんが、鍵が見つかるまで教員役以外の“女優”藤原千代子の描写がありません。
二度目の紛失の際には女優を引退し鎌倉だか葉山に引っ込んでしまい今日に至るといった具合です。
鍵とはどういった意味を持つものか?について鍵の男は言いました。
{netabare}一番大切なものを開ける鍵{/netabare}
鍵を無くした時期に失っていたもの = 一番大切なもの ということなのでしょう。振り返れば劇中劇の多くは想い人を追っている描写で埋められてました。
どこかに辿りついて鍵を開けるのがゴールだと見えてたのはミスリードで、鍵が手元にあるから一番大切なものを開放できていたのです。こちらも振り返れば、千代子は鍵をネックレスにして首からかけてました。宝箱は千代子自身だったのでしょう。
となると、回想でも劇中劇でも想い人である“鍵の男”を追っている時に女優藤原千代子の人生が輝いていたと言えます。恋に恋してという陳腐さではありません。
{netabare}想い人を追う現実の自分{/netabare}
{netabare}想い人を追う演技をしている役の自分{/netabare}
“現実”と“虚構”が溶け合いました。導き出される答えは女優という職業に人生を捧げた一人の女性の凄味です。そして女優という職業の業の深さでしょうか。
そもそも“鍵の男”がちょんまげ姿で登場した時点で気づくべきでした。想い人は何かしらの象徴的な意味合いを持ち、好きな男を追いかけるシンプルな話ではなくなっていたのです。
人生は舞台であると言ったのはシェイクスピア。
浮世は舞台でメケメケの世界と言ったのは桑田佳祐。
本作を通じて、人生という舞台を演じ切るのが大事なのでは?との問いが投げられたと受け止めることができます。
{netabare}空襲後に「いつかきっと」の石版絵{/netabare}
完成することはきっとないのだと思います。だからこその「尊き哉人生」です。{/netabare}
小難しく考えると、ラストがストンと腑に落ちるのでした。
人生を愛した一人の女性の物語です。名作と言って差し支えありません。
{netabare}みたび鍵を手にすることができた千代子は、半生を振り返るインタビューの中で久方ぶりに女優となるわけです。
病床のベッドの上で立花からの「また追いかけられますね?」との励ましに「どっちでもいいのかもしれない。」と答えた千代子。
“わが人生に一片の悔いなし”{/netabare}
最後に余談。
■どこが千年?
千年とは物理的な時間の意味に非ず?
「千代に八千代に」ずっと
「千変万化」いくらでも
で使われる“千”の意味合いが強いと思う。
■声優“荘司美代子”のお仕事
藤原千代子役には年代に合わせて三名の役者さんが声を当てられてます。
荘司美代子:70代
小山菜美:30~40代
折笠富美子:10~20代
そのうちの荘司美代子さんのお声が凛として気品がありました。調べてみたら「ちはやふる(2期)」の山城今日子専任読手の声の方だったんですね。声の仕事はあまりない方ですが印象に残る演技です。
2019.02.17 初稿
2019.08.04 修正