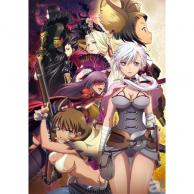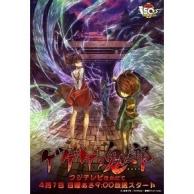みかみ(みみかき) さんの感想・評価
4.0
なんだよ、よかったよ
いろいろと評価のわかれる作品ではあるが、私はだいぶ気に入った。
作画のすばらしさがとんでもない水準に達しているのはもちろんだし、すべての複雑なプロットをいさぎよく放棄したシナリオも、…なんだかんだでよかった。
リアリティの水準の保ちかたが、観客の「鑑賞」の仕方そのものを選ぶような、わけのわからない構造になっているという気もしたが、そこを自覚的に見ることができれば大丈夫なんじゃないのかしら。
狂人、宮崎駿の何かが結集している感じでよかったですよ。ほんと。