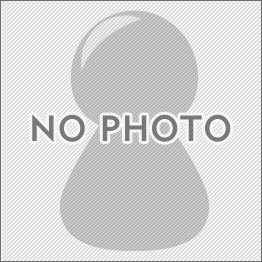キャポックちゃん さんの感想・評価
2.4
物語 : 2.5
作画 : 1.5
声優 : 2.5
音楽 : 3.5
キャラ : 2.0
状態:観終わった
SFとしてもミステリとしても未熟
【総合評価☆☆】
【ネタバレあり】
あおきえい(監督)と舞城王太郎(脚本)という才人を起用し、SFとミステリを合体させた意欲作でありながら、SFとしてもミステリとしても未熟で、アイデア倒れの感が強い。
基本的なプロットは、捜査官が連続殺人犯のイド(id)に潜入し、犯人捜しを行うというもの。犯人が不明な段階での潜入なので、現場から採集された「思念粒子」を使ってイドを再構築するという、かなり苦しい言い訳が用いられる。他者の心理世界への潜入は、ディック『宇宙の眼』などに起源を持ち、80年代に流行したサイバーパンク以降、SF作品で繰り返し用いられてきたが、本作の場合、SF的な状況説明は乏しい。それどころか、ジャルゴンを用いて擬似科学を装うことすらせず、精神分析学用語のイドと「井戸」「異土」を掛けたダジャレで視聴者を煙に巻く。ちなみに、フロイトのidは、精神を構成する要素のうち快楽原則に従う無意識の領域を指しており、明確に対象化できないため、単に「それ(ドイツ語のEs、ラテン語のid)」と呼んだらしい。本作では、殺意の根源となるイドが想定されている。
潜入できるのは殺人を犯した者に限られ、イド内部に入ると記憶を失うが、なぜか自分を名探偵だと自覚し探索を始める---こうした設定に則って、連続殺人犯の心の闇に何が潜むか明らかにできたならば、面白い作品になったろう。しかし、底知れぬ殺意がどうして生まれたかを納得のいく形で提示することができず、犯人たちが猟奇的な殺人を繰り返す理由は明確にされない。
すべての連続殺人犯のイドに登場するジョン・ウォーカーは、殺人衝動を引き起こす人間本性の具現かと思わせておいて、終盤では「こんなオチ?」とがっかりさせる姿に(某ウィスキーブランドを思わせる名前だが、本作では、酒がらみのネーミングやガジェットが多く、脚本家の遊び心を感じさせる)。繰り返し死体として現れるカエルちゃんについても、最終2話で妙にクドい言い訳じみた説明が積み重ねられるだけで、すっきりした謎の解明とはほど遠い。猟奇的な殺人や斬新な捜査方法には興味をそそられるものの、ミステリとしての結構はお粗末である。
おぞましい殺人鬼が何人も登場する中で、私が特に興味を持ったのが、被害者の頭部にドリルで穴を開ける「穴あき」。自身の頭にも穿孔があり、数への偏執のような異常な思考を抑制するために、自ら脳を傷つけたことを窺わせる。人間の大脳新皮質は、かなりの部分が損傷されても身体的な生命活動を維持できるが、損傷箇所に応じてさまざまな高次脳機能障害を引き起こす。おそらく、穴あきは、そうした障害の何かに魅力を感じて、「世界に穴を開けたい」と念じる偏執狂になったのだろう。ただし、作中で高次脳機能障害についての説明はなく、よほど深く読み込まない限り、彼の行動は単におぞましさを感じさせるだけ(第5話で特定の行動障害が脳の損傷に起因すると説明されるが、医学的に正当な主張とは思われない)。「何かが失われることが救いをもたらすか」という哲学的な問いかけは、「たこや」の文字に象徴されるように、欠失部を使った記号表現という単なるパズルにすり替えられる。
穴あき以外の連続殺人犯は、心理の肉付けがほとんどされておらず、その多くは、わざわざ登場させる必要があったのか疑問に感じるほど。物語としては、穴あきと墓掘りを深く追求するだけで、充分だったのではないか。
脚本を執筆した舞城王太郎の小説は、『阿修羅ガール』(2003年、三島由紀夫賞)しか読んでいないが、人間ドラマよりも次々繰り出される言葉の面白さを追求するタイプで、正直言って、好きにはなれなかった。あおきえい監督のインタビュー記事(ひかりTV 特集『ID:INVADED イド:インヴェイデッド』独占SPインタビュー あおきえい×碇谷敦)によると、あおきが「大人のキャラクターが主人公で、ダークヒーローものがやりたい」とプロデューサーに相談し、舞城に依頼することになったという。ところが、舞城はシリーズ全体の構成を審らかにせず、いきなり第1話から順番に脚本を執筆することを望んだ。アニメスタッフは、最終的にどんな展開になるかわからないまま制作を始めたようだ。謎めいた雰囲気を盛り上げる序盤に対して、終盤がいかにも説明口調で、表現様式が照応していないのは、こうした執筆方針の結果なのかもしれない。
あおきえいは、『Fate/Zero』『放浪息子』など数々の傑作・秀作をものしてきたトップクラスのアニメ作家だが、本作に関しては、あまり褒められる点はない。むしろ、作画は稚拙としか言いようがない。イドという心理の世界を描出する以上、その特質、例えば、パースペクティブがユークリッド的でなく遠近の感覚が失われる点や、他者の存在が不安定で立ち位置が揺らいでいることなどを、的確に表現するように配慮すべきだろう。しかし、『ID:invaded』にこうした配慮は見られず、シナリオをアニメに起こすだけで手一杯になった感じである。登場人物も、体幹の動きが捉えられておらず、棒立ち状態のまま手を動かすだけ。表情に至っては、まるで人形である。例えば、第10話で現実と非現実の境界が曖昧になるシーンは、作画がしっかりしていればそれなりに感動的になったはずなのに、人物の内面が充分に表出されていないため、同種の状況を描いた先行作品(筒井康隆『パプリカ』、押井守『アヴァロン』、NHKドラマ『クラインの壺』など)に比べると、いかにも平板で面白みに欠ける。