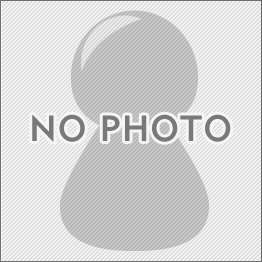ossan_2014 さんの感想・評価
4.0
物語 : 5.0
作画 : 3.0
声優 : 4.5
音楽 : 3.0
キャラ : 4.5
状態:観終わった
工業製の礎石
*少し書き足し
異世界へ転生した本好きの現代日本人が、異世界で本を求めて奮闘する物語は、おじさん好みの「異世界転生」の見本のようだ。
現代人が異世界へ放り込まれる物語は昔から数多く存在してきたが、多くは「現代人」が現代の知識や経験を生かして「異世界」で困難を切り抜ける様が、大きな魅力だった。
現実から遊離した物語世界であれば、全て広義の「異世界」と云えるわけだが、ライトノベルでは「異世界」が事実上「RPG世界」として限定されているのは、ゲーム的「世界」であれば、「ゲームに馴染んでいる」だけで何の知識も経験も能力もない人間でも、「活躍」させることが可能であるからなのだろうか。
極端な話、引きこもりでゲームだけしていた無経験で無教養なキャラでも、社会的に活動して承認や称賛を集められる物語を成立させるために、ラノベの「異世界」はゲームの模写である以外の形態を持てないのかもしれない。
本作では、ラノベ「異世界」の定型を一蹴し、「本好き」が執着する「本」を物語の基礎に置く礎石としたことで、その上に築かれる「世界」の高度な構築性と、その「世界」で主人公が未来を切り開くために「現代」の知識が活用されるダイナミズムと躍動感が生み出されている。
そんなものは単なるオジサン世代の好みであって、ゲーム知識以外は空っぽでも活躍できる異世界こそが「異世界」であり、道を切り開く為に「知識」や「教養」が必要とされる世界は居心地が悪いと言われれば、返す言葉は無い。
{netabare}本好きにとって、「本」の無い「異世界」は地獄の隣町のようなものだが、自身の根源としての「本」に執着する主人公の妄念が、物語を駆動する。
「本の無い世界」といえば、知識や思想が制限されて統制された「世界」が、条件反射的に定番として想起される。
が、本作の独創は、「コンテンツの容器としての本」という「概念」と、「大量生産」される「工業製品としての本」という「物質性」の二重性において、「本」を把握していることだ。
主人公=現代人が一般的に想起する「本」とは、「印刷」された「紙」を「綴じ」た「工業製品」だ。
「コンテンツの容器」としては電子デバイスに押され、若者からはローテクな遺物とも思われがちな「本」は、それでも機械工業的に「量産」される「工業製品」であることに変わりはない。
そうした「本」が存在しない「世界」であれば、それは「機械工業」はおろか「手工業」も存在しない、手作業の職人仕事の「世界」であるしかないだろう。
「コンテンツの容器」は、どのような「世界」でも絶対的な有用性がある。有用性のある「必需品」が存在しないという事は、「物質」として生産する手段に制限があるという事だ。
すなわち、「本」の無い「世界」ならば、「工業」があっては「ならない」。
手仕事の連鎖で「社会」が運営されているならば、政治・社会形態は「封建社会」であるだろう。
「経済」が自立的な領域として完全に確立する以前の、「仕事」は生存のための役割分担と相互補助が拡大されたものと了解される「手仕事」連鎖の社会では、ほかの政治形態は支えきれない。
こうして「本」の不在から導き出された「設定」が、「世界」の全ての描写を、高度な統一感をもって実現していく。
遊びと「仕事」が混じり合って一体となった、手縫いで作れるデザインの服を着て木靴をはいた子供たちの日常。
水道はなく食料や薪が備蓄された台所で、暖房を兼ねたカマドのわきで手仕事をする、労働と私生活の区別の曖昧な、冬季の庶民生活の描写。
庶民に「国家」が意識されることは無く、ギルドや教会に生活を調整する「権力」が分散された日常生活。
異なる社会階層の人間同士の交流の少なさと、互いの情報の不足。
矛盾なく強固に構築された、このような背景や日常の描写は、全てが、「本」に精緻に焦点を合わせているからこそ、その不在から導き出された設定もまた必然的に精緻になることによって、成立している。
一見するとラノベ「異世界」のエセ中世ふうゲーム世界に似ているかもしれない。
が、ラノベ「異世界」にありがちな、前工業化「世界」でありながら、どう見てもファスナーやニットマシンやミシンがなければ製造できない衣装デザインが登場したり、工業規格がなければ維持できないインフラの上に大人口の都市が成立しているような、わかり易い不自然はない。
「本」という1点に照準を合わせた強固な構築の意志が、本作の「異世界」を支え、程度の低い不自然が露出する事を許さない。
程度の低い不自然はすべて「魔法」という万能の一言で合理化する「異世界」が林立する中、「自由意思」による自分の人生の自己決定を求める現代人=主人公のドラマを描くために、最低限の補正として「魔法」を導入するところも巧みだ。
たとえば、支配権が「王」に集約される絶対王政以前の、ギルドや教会や地方領主に権力が分散される、「法」の効力が曖昧な社会での「契約」を成立=保証するために「魔法」を導入するところに、ドラマを支える背景/舞台として「世界」を設定する方法的な自覚性が、強く現れている。
自分の望み通りに生きられないなら生きることに意味はない、と語り、封建社会人の周囲を驚かせる主人公=現代人の言葉だが、視聴者にとって常識とも云えるこうした感覚もまた「本」に結びついている。
宇宙にも匹敵する無限の「内面」を持った唯一無二の〈私〉こそが自分の主人であり、世界に対面する責任を引き受ける、という近代人の自己認識=近代の人間像が、主人公=現代人のセリフを生み出し、視聴者の共感を呼ぶ。
ヴァルター・ベンヤミンが、「いま、ここ」の拘束を離れて単独で複製芸術に向き合う「個人」において「世界」と対峙する近代人の人間像を喝破したように、「いま、ここ」の話者の「語り」を離れて「大量生産」された「本」を独りで黙読する「読書人」は、近代人のメタファーであり根拠でもある。
物質としての「本」の生産に自己実現を見出して邁進する、自由意思に駆動される主人公=近代人の行動原理自体もまた、やはり「本」に強固に結びついているものだ。
本作の礎石に置かれた「本」のこうした多重性が、「世界」と、そこで展開される物語を支えている。
本作の物語の礎石である「本」は、このように量産される「工業製品」としての本だ。
手仕事の写本を閲覧できるようになったとしても、主人公の歩みが止まる筈はない。
周囲の「異世界」人を驚かせる、「本」に象徴される、主人公の「自由」な生を追い求める「自由意思」は、これからも周囲への「自由」の啓蒙と拡散が摩擦を引き起こすドラマを生み出すだろう。
あるいは、物質としての「本」の量産は、「手工業」を、そしてその先の「機械工業」を開拓し、「商業」の拡充を通じて「異世界」に「経済」という領域を誕生させるのかもしれない。
「経済力」という新たな「力」は、「権力」に対抗するものとして「自由」の推進力となるのだろうかと、想像を膨らませてくる。
独特の(あるいは古典的な)「異世界」の続きを、楽しみに待ちたい。{/netabare}