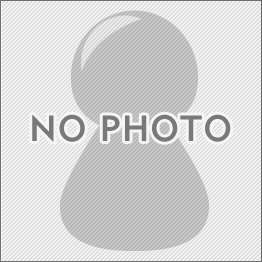ossan_2014 さんの感想・評価
4.1
物語 : 3.0
作画 : 4.0
声優 : 4.5
音楽 : 4.5
キャラ : 4.5
状態:観終わった
ギフトの使い道
【視聴完了して改稿】
監督は『COWBOY BEBOP』の監督をしていた人物だそうだが、本作の舞台が、ロスアンゼルスとサンフランシスコとシカゴを混ぜ合わせたような火星のアルバ市というのは、この監督の手癖のようなものなのだろうか。
対照的な、しかし何処にでもいる典型的な少女二人が、類まれな音楽の才能で物語を駆動する。
突出した才能は時に神から賜った「ギフト」とも形容されるが、まさに物語の駆動のために神=創造主=製作者から贈られたギフトだろう。
ちょうど『ブルース・ブラザース』の「ブルース兄弟」が、箸にも棒にもかからない「ならず者」なのに、なぜだか彼らの演奏を聴く者すべてを感動させる才能を持つという「設定」が、シカゴを震撼させる(?)大騒動を生み出すための「仕掛け」であったように、本作の「ギフト」も、少女の夢をかなえるご都合主義の道具ではなく、物語を駆動させる「仕掛け」として、まず置かれている。
{netabare}しばしば感じることだが、若いキャラ、特に若い少女の何かの「活躍」が描かれるとき、脊髄反射のように「成長」を探そうとする視聴は、楽しみを狭めるように思う。
安易な「成長」フレームは、大抵は周囲の「承認」や「威信」や「賞賛」をかき集めることで「成長」を証立てようとするものだが、本作で主人公に与えられる「ギフト」は、そうした「承認」と引き換えるための通貨ではない。
特異な才能を持った「ならず者」の「ブルース兄弟」は、「音楽」は絶賛されるものの、特異な「才能」によってならず者の蛮行が免責されるわけではない。
しかし、ハチャメチャな犯罪行為によって、彼らの「音楽」が毀損されることもまた、ない。
巨大な「才能」があっても「ならず者」から脱することができるわけではないし、「ならず者」だからといって彼らの「音楽」が葬り去られることもない。
ブルース兄弟は、「音楽の才能を持った ならず者」という、「彼ら自身」であり続けるだけだ。
本作の主人公たちもまた、ありふれた、しかし「ギフト」を持つ少女として、ありのままの彼女たちであるだけだ。
「承認」をかき集める特権性の獲得で表現される「成長」を探すのは、筋違いだろう。
どの民族、どの社会集団でも、必ず独自の音楽を持つように、音楽は人間にとって何か根源的なものであるようだ。
「全て」の人間にかかわる「根源」性が、音楽が巨大な「産業」として金銭をかき集めることを可能にする。
ストリートから出発する主人公たちは、この根源性を象徴しているといえるだろう。
与えられた「ギフト」は、この根源性が巨大産業としての「ミュージック・シーン」に接触する物語を導くための装置として、設置されている。
現代のアニメらしく、ミュージック・シーンの「産業」性は、ストリートの根源性に対立する、単純な「悪」として描かれはしない。(作品価値と商品価値は別のものだ)
音楽「産業」は、人々に音楽を「届けてくれる」ものでもある。
だがマイケル・ジャクソンが不透明な死を迎えたように、ジミ・ヘンドリックスやジャニス・ジョプリンなど、薬物や不審死はロックスターには珍しくない。
「ブルース兄弟」を演じたジョン・ベルーシも、薬物による死を迎えている。
太古の祭祀王が、人々に君臨する支配者であると同時に、危機的状況では犠牲の祭壇に上る生贄であったように、「King Of POP」マイケルもまた、聴衆に君臨する「王」であると同時に大衆の欲望を引き受ける「生贄」であったのかもしれない。
「スター」の薬物死や奇行は、無数の聴衆の感情が一人の人間にのしかかる圧力が、生身の個人では支えきれない必然なのだろうか。
着々と進行する音楽「産業」のノウハウのシステム化を反映するような、本作の、AIによる「システム」で音楽を「生産」する「ミュージック・シーン」は、生身の「個人」を圧力から救う「シェルター」であるとも解釈可能だ。
ストリートの生身の「根源」性で観客と向き合う主人公も、前半のオーディション番組の展開において既に、ストーカー化した「ファン」の思いという圧力に直面して、傷を負う描写がなされている。
だが、AI音楽「産業」の「シェルター」性は十分ではない。
AIミュージックの「顔」というパーツであるアンジェラは、終幕ではパーツであることに自足できず、「生身」の「根源」性を振り払えずに、薬物に溺れることになる。
後半では、ベテラン声優を起用した「大物」ミュージシャンが次々に登場し、世間から引退した姿や、薬物に依存した姿を、即ち「生身」の「スター」は大衆の欲望を引き受け続けきれない必然を描き続ける。
「スター」の伝統をなぞるように薬物依存するアンジェラの描写は、製作者は、音楽「産業」のシステム性を描いていながら、(或る種)古典的な、ロック「スター」が自身の生身において聴衆=大衆と向かい合う、ミュージシャン自身の「根源」性こそがポップミュージックの本質であるという、「根源」の「システム」への優位性を疑わない立場で制作していることを示している。
それにもかかわらず、現代的なミュージック「産業」シーンに対して「否」を突きつけるほど「根源」性の優位を断言しようとしない日和見的な目配りが、ラストの、「奇跡」と言いながら盛り上がりに欠けるような「ゲリラ・ライブ」の印象を生み出す。
音楽に政治を持ち込むな、という批判にもならない下らない罵言が時として巻き起こるが、システムとして音楽を「生産」するならともかく、生身のミュージシャンが「根源」の導くまま何処までも自由に手を伸ばそうとするなら、どこかで「壁」に手をぶつけるのは不可避だ。
壁を押しのけようとしなければ「音楽」はそもそも生み出せないのであって、「政治を持ち込むな」は、音楽活動の「根源」性を政治的党派性に重ねようとする「政治的な」偏見であると暴露しているに過ぎない。
「ゲリラ・ライブ」もまた「根源」としての音楽=政治性の産物であって、鋭くメッセージ性を発散している。
が、「根源」の優位性を宣言できない日和見性が、ライブ会場に「聴衆」がいないという描写を生む。
誰もが持つ音楽の「根源」性の連帯を発揮するはずの「ライブ」でありながら、それを受け止める「聴衆」が、ミュージシャンたちと対面することなく、「配信」のモニターの向こうで「鑑賞」する姿は、「根源」=「思い」=メッセージが共有される一体感の表現からは程遠い。
あたかも「消費」される「産業」システムの音楽を眺めているにすぎないかのような「観客」の描写は、音楽「産業」システムへの中途半端な忖度を示しているようだ。
聴衆とじかに対面するストリートが主人公たちの「根源」性であるものなら、観客のいない会場に舞う紙ふぶきは、「奇跡」と呼ばれる充実よりも、製作者の日和見を露わにした空虚の飾りにしか見えなかった。
それはそれとしても、現代のアニメの音楽表現の進歩は目を見張るものがある。
80年代には「ディスコ感覚」という恥ずかしい売り文句で宣伝されたアニメもあったものだが、同時代の視聴者から観てさえ、ロックに合わせて盆踊りを踊っているような、痛々しい出来であった記憶しかない。
現代では、逆に音楽のPVとしてそのまま使えるのではないかといったレベルのアニメ映像表現も珍しくはない。
技術上の進歩というよりも、製作者のセンスの向上か、センス有る製作者の業界参入の成果だろうか。
本作では、「アニメ」のメタ的な特性を随所に生かしている。
使用言語が英語である世界でも、登場キャラは(吹き替えのように)日本語で話す「お約束」をそのまま踏襲し、しかし「歌」は「原語」である英語で歌わせることによって、異なる役者と歌手が同一人物を担当する違和感を解消しているが、そもそも「絵」に対して「声を当てる」アニメのシステムを前提としたものだ。
残念ながらドラマは凡庸な落としどころに落ち着いたようだが、楽曲の出来に不満があったとしても、こうした技術性を観るだけでも一応の満足はある。
前半の「メインステージ」であるオーディション番組は、勝者が「承認」を独り占めする「勝負」の舞台というよりも、様々なミュージシャンがそれぞれの「根源」から生み出す音楽のバリエーションを展示する舞台として導入されているようだ。
『ブルース・ブラザース』で、さまざまなローカルなミュージシャンが、それぞれの「地元」で聴衆を沸かせていたように、本作のミュージシャンたちも各々の「ローカル」=よって立つ「根源」から生まれた音楽を披露していて楽しい。
音楽を生み出す「ローカル」=独自性が、単なる地域性を越え、ジェンダーやポリシーといった内面性だけでなく、SNS内の自己「イメージ」や、「産業」システムを内面化した「自分」であるといった多様性が、現代のアニメらしいところだ。
特に気に入りは何といっても「マーメイド・シスターズ」だが、あの下品な歌詞を美しいハーモニーで歌うパフォーマンスは、むかし三宅裕司の劇団スーパー・エキセントリック・シアターが出したコントCDの中の、「コンパで酔っぱらった合唱クラブが混声合唱で『ヨサホイ節』を歌う」というネタを思い出させて印象深い。
気が付くとなんとなく口ずさんでいて、これは少々まずいかもしれない。CDが出るようならぜひ購入したい。
海外でもインパクトがあったようで、ちょっとチェックしてみたら「オレのソウルの一番深いところを直撃したぜ」という感想が目に付いたのだが、まさに音楽が人の根源を揺さぶるという証左だろう(たぶん違う)。
マーメイド・シスターズが単なる色物としての登場ではないのは、対決するミュージシャンが「GGK」であるところに明らかであるように思う。
やはりぶっ飛んだ自己PRをするGGKだが、現実的な生身の自己とはかけ離れた、空想的な「設定」にアイデンティティを定めているところは「マーメイド・シスターズ」とまったく同型的だし、楽曲も『ミルキーウェイ』=天の川で、「銀河の」マーメイドとこれも対応している。
ようするに似た者同士の対決というわけで、慎重に計算していることが察せられた。{/netabare}