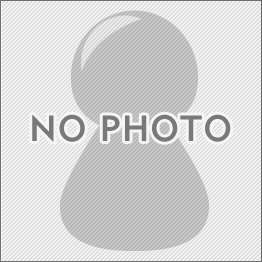ossan_2014 さんの感想・評価
4.1
物語 : 4.0
作画 : 4.0
声優 : 4.0
音楽 : 4.0
キャラ : 4.5
状態:観終わった
自尊と契約
特殊な能力を持って生れついた故に、生きる場所も理由も持てずに彷徨うヒロインが魔法使いと出会い、様々な事件や人と出会いながら居場所と自分自身を見出してゆく。
ケルト的とでもいうのだろうか、国教制定のはるか以前の悠久から数多の妖精の棲まう森と、微妙に融合したようなイギリスの田舎の風物が美しい。
最近のアニメらしく、日常的に数マイルも歩かなければならない田舎の割に車もオートバイも背景に登場しないが、英国モータースポーツの土台を支えた、田舎のガレージでオートバイをいじるバックヤードビルダーの旧車など描写されればもっとイギリス風で楽しかったのに、と、これはオッサンのただの好みの問題に過ぎないが。
「プライド」という言葉は現代ではネガティブな意味で使われているようで、持っていてはならない、良くないものとして否定的な言葉と思い込んでいる人もいるようだ。
が、言葉の字義通りの意味での「自尊心」というものがなければ、人間は自分の足で立つことはできない。
自分を甘やかす言い訳としての「自分を大事に」というおためごかしではなく、真の意味で自分の「尊厳」を自覚すること。
本作のヒロインは、生みの親からも存在の意義を否定されるという形で、最も素朴な形で自分の尊厳が芽生える契機すら奪い取られていると、巧妙に設定されている。
自尊感情が完璧に欠如した彼女は、「自分は不要な人間である」という負のアイデンティティしか持つことができないが、魔法使いに「買われる」という形で「必要とされている」という契機を与えられたことで、かろうじて死を思いとどまる。
自尊の感情を持てず、他者からの「必要」によって自身の存在意義を感じる人格設定は、一歩間違えればDV男と別れられない共依存症のようだとも思わせるものだが、それだけに暗く深刻な重さを持つものとして迫ってくる。
魔法使いによって、自分を死にまで追い詰めた異能力が大いなる「力」となる、妖精や精霊の棲む異「世界」へ導かれることで、ヒロインは次第に自尊の感情を芽生えさせ、そこで初めて他者と向き合い手を取り合える立場を得る展開は、ストンと胸に落ちてくる自然なものだ。
白馬に乗った王子様に迎えられて「お姫様」に変身する定型にも見えながら、導き手が、誰もが羨望のまなざしで見上げる「王子様」ではなく、誰もが顔を背けて視線をそらす「魔法使い」であるところが自覚的な物語創りをうかがわせる。
自立するアイデンティティと自尊感情が生み出されるのは、羨望のまなざしという他者からの「承認」を集められるからではなく、特別な「このひと」のまなざしが自分を見つめているからなのだ、と。
魔法使いの手ほどきを受け、自身の能力を開花させて自分の足で立ち上がる展開は、これも、「平凡な私」がコーチに才能を見いだされてトッププレーヤーとして「成長」する、スポーツものの定型に似て見えるかもしれない。
だが、ヒロインはトッププレーヤーとして「承認」を集めることで「プライド」を保つ「弟子」ではない。
「自尊」を回復して、魔法使いに、他ならぬこの人に手を差し伸べられるようになりたいと願う「嫁」だ。
物語が追うものは、周囲の賞賛を集める「承認欲求」に駆動される「成長」ではなく、「互いに」手を差し伸べあう恋愛であり、ヒロインの自尊の回復は、恋愛のプレイヤーとしてまず舞台に立つために要請されている。
タイトルが、魔法使いの「弟子」ではなく、魔法使いの「嫁」であることは、こうした周到な計算の産物だろう。
作中で特に強調されて主題化されることはないが、「嫁」という言葉は、背後に性行為=肉体関係を含意している。
互いに裸体を晒し、互いに互いの身体を全面的に受け入れあう「肉体」の関係を含んだ「嫁」は、愛や尊敬や信頼といった形而上的な理念のつながりに加えて、即物的な身体までを含めた「総体としての〈私〉」=「〈私〉のすべて」を受け入れあう関係を射程に入れていることを示すものだ。
自分の死の念慮というゼロ地点から歩き始めたヒロインが、他者を全面的に受け止められる自尊を築いていく様を、物語はゆっくりと描き出してゆく。
眼前の「このひと」を受け止められる足場を築き上げたとき、「世界」もまた美しく色彩豊かなものとして立ち現れるのだろう。
ただ、こうした恋愛関係が、売買という「契約」から出発する展開が、ロマン主義の影響がぬぐえないオジサン世代の視聴者には、少しとっつきにくい感じもする。
それは、「死」にすら意味を見いだせないほど空虚なヒロインを物語へと進ませるために、「契約」という外的要因を動機として要請したせいなのか。
それとも、若い女性にとっては、恋愛や結婚は「契約」の類似物として捉えることがリアルであるのだろうか。
メインターゲットではないオジサンは、少しばかり置いてけぼりの気分になる。