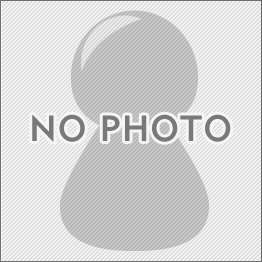ossan_2014 さんの感想・評価
4.0
物語 : 4.0
作画 : 4.0
声優 : 4.5
音楽 : 3.0
キャラ : 4.5
状態:観終わった
虐殺の言語
【微修正。大意に変更はありません】
伊藤計劃作品アニメ化の三作目。
一人称で描かれる、情報量の多い原作小説のビジュアル化に、よく健闘している。
原作から膨大な思弁を伴う重要エピソードを大きく削り、ビジュアル化可能な行動=アクションで物語を語る手法だが、思弁=言葉を大幅に制限されながら、簡易化することなく虐殺をめぐるストーリーをとりあえず語りきったとは言えそうだ。
そのビジュアルに関しては、次々に登場するガジェットやテクノロジーに過剰な解説をすることなく、映像だけで機能を理解させていく手際は見事で、製作者の映像センスの確かさを窺わせる。
世界で頻発する虐殺の謎を追う物語は、冒頭のジョージア=グルジアで、ほとんど全ての観客に理解できないであろうグルジア語の中に放り込まれる導入から始まり、チェコ、インド、アフリカと、各地の言語の中に送り込まれることで、異言語に象徴される敵性地へ侵入する特殊工作員の皮膚感覚を表現するとともに、観客に「言語」への意識を喚起する巧妙な仕掛けが施されている。
(外国へ行ったとき、現地空港に着いた途端に周囲から「日本語」が消えている事に気付き、「外国」へ来たと強く意識する感覚を思い出させる)
一方で、英語の「文書」が必ず瞬間的にしか表示されないのは、アメリカ人という設定で日本語セリフを話す主人公を観る日本語話者の観客が、英語を「読もう」として外国語=異言語だと意識してしまわないようにする計算だろうか。
外国人を主役にした日本アニメに付きまとう問題だが、本作では英語が「自言語」と了解されていなければ具合が悪い。
「言語」に対する慎重な配慮を持った描写は、勿論、本作の主題に直結しているからだ。
{netabare}特定の文法で記述される言葉によって、意思決定が「虐殺」へと誘導されてゆく。
人間の意思を操作する技術や仕掛けは、SF作品には、しばしば登場する。
本作のSF的な独創は、「虐殺」の意思決定が「脳内のスイッチが「言語」によって押されて」発生するのではなく、「意思」決定の実態が、脳内の情報処理モジュール群のせめぎあいであり、単一の自己同一的な人格の発揮する能力ではないという、脳科学的な知見を参照した、唯一無二の確固とした「私」という人間性への懐疑だ。
人格や意思といった「私」の特性が、環境に自動反応するモジュールのせめぎあいによって「動的に」生じる現象に過ぎず、「私」や「私の意思」がモジュールを誘導する「テクノロジー」や「虐殺器官」によって変貌するSF的な設定が、他者を殺す「意思」の無根拠性をも暴きだし、実存の不安という伊藤計劃的な思弁へとつながる。
原作の母親の死をめぐるエピソードが削られることで、意思決定をめぐる理論が十分に語ることが出来ず、アクション主体で進行させざるを得ない映像作品という制約の中で、本作はかろうじて「秘密の脳内スイッチ」といった単純化に陥ることを免れ、最低限の設定を描写することには成功している。
しかし、量的に少ない脳内モジュールの「説明」からは、虐殺を発生させる「器官」が現代では必然性がないように、虐殺=他者を殺すと決意した「殺意」さえも、モジュールのせめぎあいの上に浮かぶ、必然性のない廃棄可能な泡に過ぎないという批判性までは、少し見えにくい。
モジュールの動き一つで、虐殺を「しない」という「意思」もまた、何時でも発生するほどに「人格」は不確かであるという批判性。
そして、アメリカに虐殺の文法を流通させる主人公の「意思決定」もまた、環境に反応するモジュール群の運動の産物である以上、アメリカ(および先進工業国)という「環境」に反応した「私」、の「物語」に過ぎないという、本作オリジナルのラストの批判性。
(言葉の断片を「文法」通りに配列して「虐殺の言語」を探る作業を表現する、附箋紙に覆われたボードは、「意思」を析出する脳内モジュール群の運動モデルとパラレルの巧妙な描写だ)
引き起こされている惨劇がどれほど悲惨なものであるか、「虐殺」という強い言葉の使用で想像させるだけで、十分に具体化されているとは言えないため、全体として、ややゲーム的な追いかけっこに見えがちになり、余計にこのラストの批判性の衝撃が見えにくくなっているようだ。
主要人物や少年兵のように、感情移入する固有性を持った死によって悲惨さを表してしまうと、個人の死が埋没する大量死である「虐殺」に特有の悲惨がぼやけて、ゲーム感を強める。
明らかに「悪」である、射殺される少年兵の「明確な感情」を想起させる死は、「明確な」目標と「明確な」得失点のルールが設定された「ゲーム」に親和的で、個別の死者に対する個別の理由が明確でないまま大量死が累積する「虐殺」の、不定形な得体のしれない不気味さから遠ざかる。
具体的な大量の死体の描写はしなくとも、もっと惨劇を想起させる表現の仕方はあっただろうと、少し惜しい気持ちを感じさせた。
虐殺をモチーフとした、脳科学と進化心理学に依拠したSF設定の描写は、映像作品にとっては確かに表現上の制限は多いが、人文的な視点からでも、本作の解読を試みることはできる。
人間をなぜ殺してはいけないのか、という問いに対して最もシンプルな答えは、「人間は人間を殺さない性質があるからだ」というものだろう。
「殺してはならない」という法があること自体が、人間は人間を殺す自然な性質が備わっていないという証明ともいえる。
殺すことが、人に備わった自然な性質で、不可避に常に発生するものであるならば、そもそも「殺してはならない」の法は発生しない。
「水を飲んではならない」という法があり得ないように、「殺すな」の法は発生=発想のしようが無いだろう。
そもそも「殺さない」からこそ、「イレギュラー」の発生に備えた法が発想される。
しかし、にもかかわらず太古から部族間の闘争=戦争は絶えない。
伝統社会の言語の研究によると、伝統社会では「人間」を表す言葉と、その部族あるいは「われわれ」を表す言葉は、しばしば共通しているか関連している例が見られるそうだ。
そう、「人間」同士は、「われ-われ」同士は、互いに殺し合わない。殺す「性質」を持たない。
殺せるのは、「やつら」が、われわれ「ではない」=人間「ではない」からだ。
「人間」でないものは、殺せる/殺しても構わない。
現代において、戦争で「敵」を殺すことに無条件で納得できない=抵抗を感じるのは、「敵」もまた「われわれ」と同じ「人間」であると把握されているからだ。
地上の人間は全てホモ・サピエンスという単一種であるという生物学的知見や、人権という社会思想が広範に共有、認識されることにより、現代人は敵対する敵であっても同じ「人間」であるという信憑を強固に抱いている。
したがって、現代において敵を殺す、あるいは虐殺をするには、まず相手は「人間」では「ない」と規定しなくてはならない。
ナチスはユダヤ人を「シラミ」と呼称した。
中国共産党は文革の弾圧実行に際して、敵対者を「害虫」と規定した。
ルワンダのフツ族はツチ族を「ゴキブリ」と呼んだ。
最大限の侮蔑の表現として「犬」や「豚」といった言葉を使用する言語はいくつもある。
虐殺に先立って、まず相手を「人間」以外の呼称で呼ぶこと。それは現実世界の「虐殺の言語」だ。
もしも、特定国の国民や特定集団を人間以外の動物の名で呼ぶような言説が広くみられるようになったとしたら、それは「虐殺の文法」が作動し始めた予兆であるということかもしれない。
こんな観方をしても、本作の虐殺の言語をめぐる物語に、リアリティを追加することが出来そうだ。{/netabare}