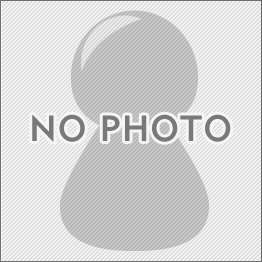ossan_2014 さんの感想・評価
3.9
物語 : 4.0
作画 : 4.0
声優 : 4.5
音楽 : 4.0
キャラ : 3.0
状態:観終わった
饒舌の意味
同シリーズの他作品同様に、ゲーム的にタイムリミットとクリア課題を明確に設定して、一気に畳みかけるようにドラマを進行させる。
中盤での、探偵小説の叙述トリックのように、見えている「世界」の意味が転倒するような「仕掛け」の後、最後のステージクリアへ向け、一点に集中していくエピソードの展開が巧みだ。
本作を視聴していてまず気付くのは、早口で捲し立てられる台詞の洪水だろう。
台詞が「中二」的な単語で構成されていることと相まって、小劇場のアングラ芝居の掛け合いをイメージさせるが、この過剰な言葉の洪水は、ある対談集での押井守の発言を思い出させた。
その対談の中で、押井は、最近の視聴者は表現を解読する能力が無くなりつつある、といった意味の発言をしている。
スタッフや観客と接する中で、「セリフで言葉にしてくれないと分らない」と、どれほど平易な映像的な比喩表現であっても否定されることが多い、と。
言葉で説明しないものは「難しい」あるいは「分らない」と一蹴されるなら、映像演出というものはもう成立しないのではないか、という危機感が押井守にはあるようだ。
本作のセリフの洪水は、あたかも、この押井の現状認識に対する一つの回答のようだ。
溢れ出す、登場人物たちの過剰な饒舌は、「全てを言葉で説明」しなければならない要請から生じている。
事件の背景、個々人の思考、進行中の事態の解説、疑似科学的な設定。
全てを「言葉で説明」するために、あのような過剰な分量のセリフが必要とされている。
本作は、言ってみれば映像ではなく、「言葉」によって物語を構成しているのだと言えるだろう。
冒頭に記した、中盤での{netabare}(主人公と主要キャラはすでに死んだ「幽霊」であったという){/netabare}
「叙述トリック」的な仕掛けは、まさしく「叙述」トリックのように「言葉」による「仕掛け」だ。
ここで視聴者に驚きを与える「世界」の転倒感は、映像によって表現されたものではない。
見えている「映像」の意味を、セリフ=言葉によって「解説」されることで成立した「衝撃」だった。
このように、本作内の表現は、映像で語っていくというよりも、常に「解説」するセリフによって、視聴者に映像の意味を「教えて」いくスタイルで作られている。
過剰な饒舌と言えば、古いアニメファンであれば『うる星やつら』の「メガネ」を連想するかもしれない。
「メガネ」の饒舌は、キャラづけとして、性格を「暗示」する演出の一環であったが、本作においては、饒舌は即物的に「説明」として持ち込まれている。
「メガネ」を創造した押井守と現代の視聴者との距離が、この「暗示」と「説明」の位相差に現れているようで興味深い。
過剰な「説明」セリフを、「小劇場のアングラ芝居」的に見せていることが本作の娯楽性への配慮を示しているが、この印象は台詞に重なる映像が「前衛的」なイメージ与える構図やカット割りを採用しているからで、いわば「言葉」が「映像」に修飾されていると言っていいだろう。
エキセントリックな「メガネ」の映像の修飾として「饒舌」を持ち込んだ押井との位相差が、ここにも表れているようだ。
言葉による「説明」を必須とするのは、押井が懸念する「能力」の低下というよりも、このところ急激に表面化してきた、「鑑賞」するのではなく「与えてもらう」視聴スタイルの現れであるようにも思える。
いや、スタイルの変化が能力の低下として現れるのか。
鑑賞によって感動が「湧き上がる」視聴から、視聴という手間と「引き換え」に感動を「もらう」視聴へ。
描かれているのは何か、「正解」を受け取らなくては手間との「交換」が成立しない。
自分の「鑑賞」に任せているだけでは、「正解」が「もらえて」いるのか保証されないだろう。
確かに「もらって」いるという保証として、「正解」は「言葉」で説明されなければならない。
説明的なセリフ回しを極点まで展開した本作だが、鑑賞される表現物ではなく提供される消費物として、映像作品は、この方向へと進んでゆくのだろうか。
押井守のような卓越したクリエイターの直観には、説得力がある。
視聴者を安心させる本作の「言葉」による「解説」だが、しかし別の見方をすると、キャラの「セリフ」でしか「説明」出来ないという限界性がある。
比喩として挙げた「叙述トリック」だが、「叙述」を「トリック」として成立させるのは、キャラの「セリフ」は事実的な「真」と一致しているとは限らない、という叙述の構造自体だ。
キャラが「真」だと発言することは、事実的な「真」を無条件で保証しないという構造。
畳みかけるような「説明」と共に真相に達した本作だが、それを構成する「言葉」はキャラの信じる「真相」=セリフに過ぎない。
キャラが「真」と信じている「事実」が本当に「真」かは、作品に内在する視点からは決定不能だ。少なくとも、「叙述トリック」を作中で使用している以上は。
果たして妄想じみたオカルトを「説明」する「セリフ」はすべて「真」だったのか。本当に「正解」は視聴者に「与えられ」たのか……
「正解」を手にしたという視聴者の安堵は、必ずしも盤石ではないかもしれない。
映像を言葉による解説の支配下に置いて、綺麗に閉じた本作。
しかし、視聴者に作品の「正解」を「与える」ために言葉による解説を義務付けられる映像作品という方向には、まだ「解説」という縛りから逃れ出るその先の方法が、期待できそうだ。
と、思いたい。