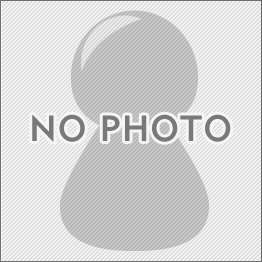ossan_2014 さんの感想・評価
3.4
物語 : 3.5
作画 : 4.0
声優 : 3.0
音楽 : 3.0
キャラ : 3.5
状態:観終わった
与えられるキズナ
【2016/06/26視聴完了して改稿】
傷、絆、ナイーブと、さまざまな連想を含意したタイトルだが、根底にある、痛覚の共有を強制するキズナシステムは、いかにもいかがわしい。
愛国心の発露として愛国的な行動をすることは普通だが、愛国的な行動を強制することで愛国心を生じさせる、と言えば反射的に嫌悪感を生じさせるだろう。
システムを推進しようとする作中の「市長」の言動の気色悪さは、ここに由来している。
が、痛みを共有させることによって心を通じ合わせるシステムは倒錯的であるものの、このような、いささか安易な例え話にとどまらない不気味さをはらんでいる。
アニメ系ラジオで読み上げられるリスナーのメールによると、最近の視聴者にとって、アニメ作品は「拝見させていただく」もので、感動や勇気を「もらう」ものであるらしい。
昭和の言語感覚からすると、アニメは主体的に「視聴する(百歩譲って、拝見する)」ものであり、感動も勇気も自分の中に「生まれる」あるいは「湧き上がってくる」ものだ。
特に、「感動」のような自身の意識の中の情動まで外部から「もらう」という受動的な表現をしてしまう事には大きな違和感がある。
これが、単なる言い回しの流行に追従できない頭の固さだとは思えないのは、比較的最近に登場した新型の鬱病において、気分の落ち込みが患者にとって「不意に到来する」ように捉えられているという精神科医の報告があるからだ。
従来の鬱病であれば自分自身の気分の変化として把握されていた「落ち込み」が、他動的にどこかから「与えられる」と感じられる新型の鬱病の流行は、自分自身の内部の「感動」をアニメから「もらう」と表現することと無関係なのだろうか。
「もらう」という表現に違和感がなく、実感を表すものとして使用されているとしたならば。
キズナシステムの送り込む「痛み」によって「絆」が生じ始める事態に、さほど違和感がないらしいキャラクターたちの描写は、「感動」を「もらう」視聴者にシンクロしているようだ。
行動主義心理学のテキストをそのまま引用したかのようなシステムの基本が「痛み」という不快によって駆動される設定は、心理学的な「マイナスのストローク」と符合していて、これも精神医学的な統一感をもって感じられる。
このような印象をもたらすものは、システムを推進する法子の描写がどこか拒食症を連想させ、ゆるキャラが神経症的な強迫を感じさせるような、一種病的なイメージを感じさせるからだ。
{netabare}外見的な美のためにダイエットをすることは、ありふれた行為だろう。
体重計の目盛に一喜一憂することも、ありふれている。
が、目的が外見上の美であるならば、指標とするべきなのは、例えばウエストや太ももの「太さ」や、あるいは「体脂肪率」であるはずだ。
体重の「重さ」と、「太さ」や「体脂肪率」には、確かに大きな相関関係があるが、ダイレクトな因果関係は無い。
体重が減っても、必ずしも「太さ」が減るとは限らないし、「体脂肪率」が悪化することすらある。
にもかかわらず、ひたすら体重計だけを見つめ、体重の減少を自己目的化して数値の低下だけを追いかけるのは、目的を見失った倒錯的行為だ。
他者とキズナが結ばれていると感じるとき、他者の痛みを自分のことのように甘受することはある。
確かに因果関係はあるが、痛みを共有することでキズナが生じるという倒錯は、体重が減りさえすれば美しくなるという倒錯と同型的だ。
法子の拒食症的な印象は、ここから生じるようだ。
何が何でも痛みをつなごうとする執念は、ひたすら体重を減らそうとする妄執を連想させる。
原因と結果/目的が混濁した倒錯を。
キズナシステムが法子の妄執であると描写することで、最終的に、システムは倒錯であったのだと本作は結論付けているように見える。
が、キズナの絶対性、「つながり」が絶対的な価値を持つという盲目的な信憑は、疑われることがない。
自身の中に感動が「湧きあが」り、他者も同じく感動が「湧き上がって」いると感じられるとき、絆を感じることもあるだろう。
が、外部からキズナが生じることも、確かにある。
例えば、「みんな」で「敵」を袋叩きにするとき。あるいは、部活で「みんな」で理不尽なシゴキに耐えるとき。
このような体験を通じてキズナが生まれることも、経験されるかもしれない。
が、感動が「湧き上がる」個人であれば、このキズナを拒絶することもできる。
「変わりもの」という烙印と引き換えに、「お前たちとつながるのは御免だ」とキズナを結ばないことが可能だ。
最終的にキャラクター全員がキズナを受け入れる結末は、どのように「与えられた」物であろうとキズナはキズナであると、キズナの絶対性を目的化しているようだ。
ラストで痛みを自らのものとして取り戻した主人公は、感動を「もらう」のではなく、「湧き上がる」主体への復帰を思わせる。
が、最終的にシステムによって「与えられた」キズナを拒絶するメンバーは出ない。
主体的にキズナを「選び直した」様に描写されてはいるものの、それはキズナ自体を無前提に無限肯定することによる、自己欺瞞的な倒錯を感じさせるものだ。
システムによって外部から他動的に生じるキズナが、一つの契機として肯定的に受け止められるとしたなら、パッケージ化して差し出される「感動」を「もらう」ことでしか「感動」を感じられない感性から離脱しているとは言えないだろう。
作劇上では、「湧き上がる」感動をそれぞれに抱える独立した主体同士が、共感を通じてつながる未来を描いているものの、キズナの絶対化がそれを曖昧化しているようだ。
キズナが絶対化されることが疑われない作品世界は、感動が「与えられる」ことが疑われない現代性に影響されているのだろうか。{/netabare}