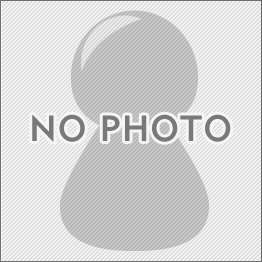ossan_2014 さんの感想・評価
3.8
物語 : 4.0
作画 : 3.5
声優 : 4.5
音楽 : 3.0
キャラ : 4.0
状態:観終わった
教師の役割
【視聴終了。末尾に蛇足追加】
原作は同名のライトノベル。
原作小説は相当に支持が大きく、ずば抜けて大量に売れているそうだが、中々に驚くべきことだ。
超現実的な設定はない。
超常的な能力は登場しない。
非日常的な事件は起こらない。
加えて主な主題が「自意識と世界の関わり」、という事になると、これは純文学の領域と大きく重なっている。
橋本治が『桃尻娘』で文壇に登場したことを思えば、これが大量の読者を獲得していることに文芸界はもう少し注目してもいいと思うが、このような小説が原作である本作が「文芸映画」の性質を帯びるのは当然かもしれない。
学生時代の記憶はすでに遠く、「スクール・カースト」や「友達地獄」に何の実感も持てないにもかかわらず興味深く視聴できてしまうのは、「文芸」アニメらしく現実的な世界、とりわけ社会性が強固に構築され、その内部で展開される自意識のドラマを封じ込めて、空虚に拡散してしまうことを防いでいるからだろう。
アニメでは珍しくない、大人がほとんど登場しない作品空間だが、その世界の強固な社会性を単独で担保しているのは、ほとんど唯一の「大人」、平塚静教諭の存在だ。
三十路手前で婚期が過ぎ去りつつあることに焦り、ラーメンやスポーツカーといったオッサン的嗜好を持ち、たぶん酒好きな女教師の造形は、ラノベやアニメではありふれている。
ただ一つ、類似の女教師の中でおそらく彼女だけが持つ属性は、平塚「教諭」が教師という「職業人」であることだ。
職業に就くという事は、単に収入のために労働をすることだけを意味しない。
仕事とは、社会においての(RPGのような)役割〈ロール〉でもある。
「勇者」という役割〈ロール〉を引き受けるがどのような個人であれ、「勇者」である以上、勇者としてのロールを果たすべく行動せざるを得ない。
実社会の職業人も、例えば警察官であれば、「警察官」という役割〈ロール〉として、勤務時間中とあらば、落命するかもしれない危険な修羅場へと突入することもある。
それは勇気ある個人が英雄性を発揮しているのではなく、ロールとしての「警察官」の自然な行動だからだ。
どのようなものであれ職業は、社会参加する大人にとって、個人を超えた、そのような役割〈ロール〉としての側面がある。
本作の平塚教諭が奉仕部の面々に相対するときの態度は、常に「上から」語り掛け、「指導する」形をとっている。
他作品に登場する類似の「先生」のように、生徒と同じ次元に下降し「仲間」としてふるまうことがないのは、おそらく彼女のみが、記号としての「先生」ではなく「教師という職業人」であるからだ。
自分たちと同じ立場で同化する「先生」は、生徒にとって一見理想的だろう。大人が消えた学校空間は、生徒=子供たちの欲望を阻むもののないパラダイスには違いない。
「子供のパラダイス」的世界の設定の為、「先生」の「友達」化は要求されるとも言える。
だが子供と同化した「先生」には、子供を「教育」することができない。教え、導く為には、時には子供の欲望を遮って、「上から」道筋を指し示すことが不可避だからだ。
教育するという役割〈ロール〉を果たす「職業人」である以上、教師は生徒の「友達」として肩を組んでやるわけにはいかない。
生徒にとって抑圧的、権威的にふるまうかは役割〈ロール〉を果たす個人の資質の問題で、ロールとしての「教師」は、どのようなやり方であれ生徒の「上に」立たなくては機能できないのだ。
平塚教諭の個人的な心情が漏れ出す描写が多々あるにも関わらず、職業人である彼女のロールが、奉仕部員の一員として同次元でふるまうことを許さない。
作品内的にそれが了解されている結果として、平塚教諭が「上から」「指導する」することに、奉仕部員たちは異議も反感も持つことはない。
逸脱的に個人としての交流がいくつもあるとはいえ、「生徒」がそれを盾に対等な態度をとろうとするならば、平塚教諭は役割〈ロール〉として即座にはねつけることだろうし、生徒もまたそのような期待はしない。
そのような「公私混同」が許された瞬間、物語世界の構造は、それが許されない現実世界のものとは、あからさまに別の形に変質してしまうだろう。
このようにして大人のいない物語世界の社会性は、社会的役割=ロールを人格的に体現する「職業人」平塚教諭が配置されることによって、保証されることになる。
出来上がった、現実に似た形の堅牢な枠の中でこそ、文芸アニメの「自意識」のドラマは、「等身大」のものとして歪まずに見せることが可能となった。
こうして整えられた「舞台」でのキャラクターの「芝居」が、文芸アニメの興味を支えていくことになるが、まずまず成功しているといえるだろう。
しかし、絵と声の両面から上手に構成される「芝居」だが、ごくわずかに違和感を感じる部分はある。
絵柄にこだわって視聴する方ではないのだが、「腐った眼」と作中で何度も言及される主人公、八幡の眼つきが、2期になって変更されたキャラデザインでは、周囲を睨みつけているような印象を受けてしまう。
八幡が周囲に対して「侮蔑」や「幻滅」を抱いているのは確かで「腐った眼」はその表れであり、セリフや声優の演技もそのように表現されているのだが、この「睨みつける」眼つきは明確に「敵意」を感じさせて不調和を生んでいる。
集団に社会的なルールは付き物だが、ルールはそれに従わせる「力」があって初めて「ルール」として成立する。
例え承認しがたいルールであろうと、「力」を覆すことが出来なければ従わざるを得ない。
だが、強制されてルールに「従う」ことと、ルールを「好きになる」ことは別の問題だ。
自分の力が足りずに「従う」よう強制されることを退けられないとしても、「好きになる」よう強制される理由は、本来は無い。
しかし、「嫌いな」ルールを無視できないのは強制力を覆す力が自分に無いせいだ、と自覚することは、「自意識」への拷問のようなものだ。
強制力を覆す「力」を持てないのならば、この拷問の苦痛から逃れる道は2つしかない。
ルールの存在を知らない無知を装うか、ルールを「好き」になること。
本作の八幡的な「カッコよさ」の核心にあるのは、無知を拒絶し、ルールの存在を見据えながらもこれを「嫌い」続けることによる苦痛を敢えて引き受けるという決断であり、苦痛に引き裂かれようが「こんなルール」など決して「好き」になるものかと叫ぶ「自意識の化け物」の決意だ。
「腐った眼」が表現する侮蔑は、ルールが欠陥だらけなのは明らかなのに、自覚的/無自覚的にこれが「好きだ」と思い込んで苦痛を回避しようとする、俗人の姑息な欺瞞への怒りが根底にある。
だが、「睨みつける眼つき」が喚起する「敵意」の印象は、単に自分が疎外されていることに対するルサンチマンに過ぎない感じをもたらしてしまい、八幡的「カッコよさ」を目減りさせてしまうように思われる。
アニメ鑑賞としては変則的だが、声の芝居の方へ注力して視聴をすることで、盲目的な敵対ではなく、状況を窺いながら「強制力」へのゲリラ攻撃を仕掛ける八幡のパルチザン的な自意識のドラマは、より深く味わえる気がする。
【追記】
後半、ドラマが内面の描写よりもシチュエーションを展開させるだけに傾いて、ちょっと駆け足気味だったのが残念。
中途半端なところで終わった感じがするが、雪乃の抱える問題は、少女の自立というよりも深刻なドメスティック・バイオレンスのように見える。
雪ノ下陽乃のキャラ設定と言動を箇条書きに抜き出すと、DV加害者に多いコントロール・フリークや反社会性パーソナリティ障害の典型的な症例と一致しているようだ。(その意味で、最終回の、「加害者」と「被害者」の物理的接触を回避させる結衣の対応は、実に理に適っていたといえる)
第3期があるとすれば、雪ノ下家のDVの解決が描かれることになるのだろうか。
それにしても若者の自意識のドラマは、なかなか感じさせるものがある。
最後に、感想に代えて、平塚教諭を仮想して八幡へのエールを送ってみたい。
平塚教諭には、おそらく八幡が囚われている「ホンモノ」の正体が見えている。
示唆的な言葉しか語らない/語れないのは、それは指し示して教えることができないものなのだから、という苛立ちが彼女にはある。
が、それは「人それぞれに答えがある」といったおざなりな逃げ口上からくるものではない。
それは、何を「ホンモノ」と看做すかという価値観の問題などではないからだ。
「ホンモノ」であると証明しようとすることは、不可能な企てだ。
「証明」とは、ある認識が客観と一致していると示すことだが、認識が生じる主観と客観とを同時に見下ろして見比べる「視点」は主観の内部に仮想として設定されるしかない以上、どこまでいっても主観の外部である客観に到達することはできないどころか、そもそも客観が「ある」ことすら明示できない。
科学は「客観」の存在と仮想的な視点を「実在する」と「仮定し」た上に構築される論理体系だから、科学と同型的な論理上での「証明」は、自意識の領域では何も明らかにはしない。
確実な「証明」を求めてどこまでも疑ってしまう八幡の「ホンモノ」探求は、疑いの根拠を「証明」の確かさにおいている限り、どこまでも袋小路に追いつめられるしかない煉獄のようだ。
奉仕部の部室で差し出された紅茶を美味しいと感じるとき、飲んでいるのが「紅茶」であるのか、どこまでも疑うことが可能だ。
紅茶ではなくハーブであるかもしれないし、味覚に異常がありコーヒーを紅茶と勘違いしたのかもしれない。あるいは只のお湯を差し出されただけかも。
いかに「紅茶」に違いないと「証明」されたところで、証明が原理的に客観へ到達できない以上、どこまでも疑いは排除できない。全く同様に「紅茶」では「ない」という証明もまた、挫折する。
だがしかし、紅茶を飲んで「美味しい」と感じたことは、疑うことはできない。
信じ込むこととは全く違う。それは「疑うことができない」。
飲んだのが真に「紅茶」なのかどこまでも決定できないとしても、それを飲んで「美味しい」という感覚を持ったことだけは、どのようにしても疑うことは不可能だ。
そのとき、部室で「美味しい」紅茶を飲んだと「感じた」ことは、不可疑なのだ。
「ホンモノ」は、この不可疑性の方向にしか存在しない。
「証明」によって「ホンモノ」の疑いを消すことはできない。いや、疑えるかどうかという「論理」の上には基礎づけることはできない。
どうしても疑えない「不可疑」の上にしか、「ホンモノ」を見出すことはできないだろう。
そのために求められるのは、より一層、どこまでも息をつめ自意識の「中へ」潜っていくことだ。
「証明」の確かさを問い続けるのではなく、より深く自分の底へ「疑うことのできない」ものを探しに降下すること。
「外」から語り掛け、それを「指し示し」てやることはできない。
がんばれ、八幡。