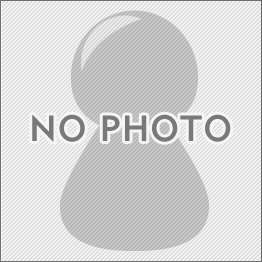ossan_2014 さんの感想・評価
3.2
物語 : 2.5
作画 : 3.0
声優 : 4.0
音楽 : 3.5
キャラ : 3.0
状態:観終わった
空気の色
最後まで視聴したが、何とも割り切れないものが残る。
{netabare}不可解な猟奇殺人事件の捜査を通じ、一連の事件が、猟奇的な快楽殺人ではなく支配システムへのパルチザン闘争であることが暴露されてゆくサスペンス・ミステリーだが、捜査からやがてシステムの防衛へと至る、常守と管理下の執行官たちの行動が、何に支えられているものなのか最後までうまく了解することができなかったからだ。
作中でミシェル・フーコーに言及されているように、シビュラ・システムは生権力をSF的に可視化した、監視/コントロール権力として描かれる。
視聴者による外部の視点からはいかにもいかがわしく抑圧的な権力は、生権力らしく作品内世界では根拠が疑われることなく、一般市民によって「色相」による選別の正当性が懐疑されることもない。
だが、シビュラの無根拠性と独善性を既に知ってしまった常守と、システムにより社会外へ排斥されている執行官たちは、視聴者と同じ視点に立つ条件を持つ。
にも拘らず、常守チーム、とりわけ執行官たちが、職業意識をもって、主体的な意思をもって捜査に取り組んでいるように見えるのは何故なのだろう。
システムによって社会から排除され、選択の余地なく執行官の立場を強制されている設定にしては、自覚的な意欲をもって社会を防衛しようとする姿はひどく不自然に感じられ、説得的な理由を作品内で発見することはできない。
システムの根幹そのものへの否定を突きつける犯人の動機の有根拠性と、システムの無根拠性を共に理解する常守が、なおシステムの手順にしたがって事件を処理しようとする理由についても。
作中では、一応のところ彼女たちの行動原理は「秩序」を守ることであるように読み取れはする。
代替えのシステムがない以上、秩序を崩壊させないためには、当面シビュラを壊滅させるわけにはいかない。
だが、この公安的な秩序は、単に「犯罪」(シビュラ的なものではなく、単純に暴力事件などの刑事犯罪)が生じていないという事態を指しているに過ぎない、皮相で表面的な印象しか持つことができない。
この表層的な秩序の維持の為には、「色相」悪化の恐怖によってセラピーに依存する大量の市民の群れと、いかがわしい基準によって社会不適格者として葬られる者たちが不可避であることは、作品内で描写されている。
社会や他者といった外部へ向かうことを、システムによるコントロールで「自発的に」抑圧される暴力は、「色相」を保てない自身への攻撃として現れざるを得ない。
全市民の(潜在的な)強迫神経症患者化と原理的に根絶できない社会不適格者を生贄として要求する「秩序」は、秩序と呼ぶに相応しいものなのだろうか。
生贄として排除された存在である執行官が、捜査と執行という権力をふるい、これを支える自覚的な意思を生み出す基盤として、十分な納得をもたらしてはくれなかった。
シビュラのグロテスクな印象をもたらすのは、「正義」に執着し、自らのそれを絶対視して疑いを持たない独善性だが、常守と執行官たちは、正義の代わりに「秩序」を代入しているにすぎないように見えてしまう。
終幕で、シビュラに突き付けられた例外状況は、これを取り入れたシビュラを変質させていくことが暗示され、変質に希望を託すように語る常守だが、シビュラの「正義」を最奥で担保しているのは「秩序を保つ」ことである以上、変質は、支配システムの構造を維持したまま、より一層の管理の強化を意味するだけのようにしか思えない。
「正義」の基準が微修正を遂げたところで、支配の構造そのものが変化することはない。
コントロール権力が一層完成され、人々に内面化されていけば、権力の命令と個人の欲求は区別なく混濁していき、セラピーに依存することすら無くなっては行くだろう。
だが、それは「秩序」の安定ではなく、生権力の完全な支配を示しているだけではないだろうか。
結局のところ、「秩序」=生存のためのよりよい環境である以上、常守の秩序を守ろうとする意思は、生権力とその抑圧を承認することにしかなっていないように見える。
この納得のいかなさが、生権力をよく可視化できていることの証だと、言って言えないことはないかもしれない。生権力を覆すことのできない無力感を描こうと、最初から計算ずくで製作されていたとしたならば、の話ではあるが。
「空気」を読んで調和を保つことが絶対視される国のアニメでは、由来も知れずに押し付けられる「色調」を疑わずに秩序に奉仕する世界を覆すことはできないのだ、とは思いたくない。
第1期の脚本家の、別作品での成果を知る限りは。{/netabare}