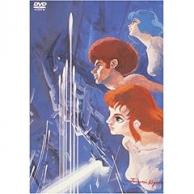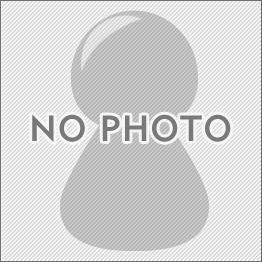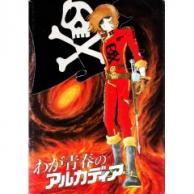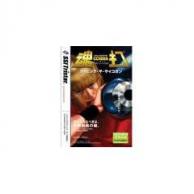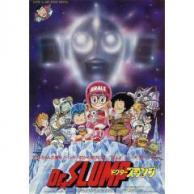たわし(爆豪) さんの感想・評価
4.4
追悼 すぎやまこういち先生
宮崎駿や庵野秀明、押井守、そして富野由悠季が何故「巨匠」なのかといえば、
世界を善悪で「単純化」せずに捉えるその姿勢に「作家性」というものを感じるからである。
昨今のアニメに決定的に足りないのはこの「姿勢」にあり、まるで竹を割ったように単純な企画しか通らない。。もしくは「観る側」の劣化が伺える。
人間がいる以上、そこに単純な善悪を持ち込めば誰かが「勝った」誰かが「負けた」といった二分化する危険思想が芽生え、第一次世界大戦や第二次世界大戦がそういう思想によって引き起こされたことを学ばなければならない。
明るく楽しい作品も結構だが、哲学なき芸術に明日はないのだ。
すぎやまこういち先生がお亡くなられたと聞いて、一番最初に思い出したのが、ドラゴンクエストではなく僕は「イデオン」である。イデの発動から弦が飛ぶの躍動感。そしてエンディング曲の「コスモスに君と」はアニメソングの中でも屈指の名曲だと思う。
謹んでご冥福をお祈りいたします。