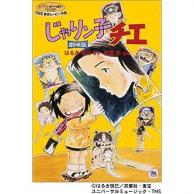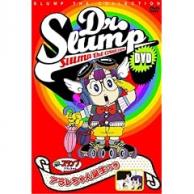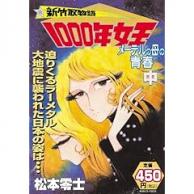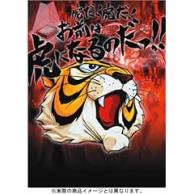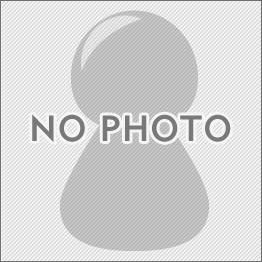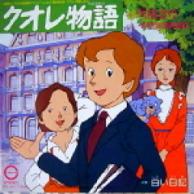タイラーオースティン さんの感想・評価
4.2
巨匠高畑監督の最高傑作
演出も作画も、恐ろしいほど優れたテクニックで良い意味で全く子供向けではない。
例えば猫の動きの表現にも、ごまかしがなく、本当に当時のアニメーターのレベルの高さを感じます。
高畑勲監督の特徴だと思うのですが、ストーリー上はもっとテンポがあった方が見やすいと思えるものを、微妙に「間」を入れることで、人間の営みを一歩引いた感じで考えさせてくれます。
例えばテツの行動は、まともな演出ならギャグそのものですが、何を考えどんな人生を生きてきたんだろうかとふと考えさせられます。
この作品が海外で評価が高いのも納得します。人物に感情移入しすぎて日本人ならわかると省略する部分を丁寧に描いているから、海外の人にも理解しやすいのだと思います。
こんなレベルの高い作品でも、ペコちゃんやゴジラが堂々と出てくるのは、おおらかな時代だったと思います。
こういう遊び、今の時代では見られません。
これを今まで見ていなかった自分も恥ずかしいですが、全く今の時代でも古さを感じないので、老若男女見てほしい作品です。
特に遊園地のシーンは素晴らしい情感で、名シーンだと思います。
遊具のひとつひとつを詳細に研究しているのが想像できて、この監督のこだわりの凄まじさを感じます。
これだけの労力を費やしているからこそ、古さを感じないのでしょう。