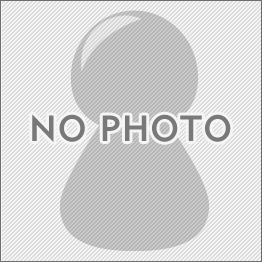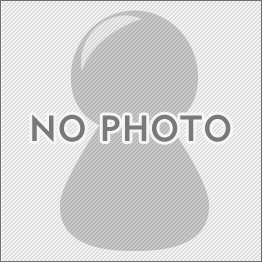原作読破済。アニメはパラパラと見ますた。
だいたいは原作に忠実みたいなので、そういう前提で。
※ちなみに下記、完全ネタバレ前提ですので。夜露死苦。
【感想要約】
兵器萌えのミリオタ作品。スタイリッシュ・ガンアクションとしては、クオリティが高く、単にそういったエンタテイメント商品としてはそれなりに良い作品。
ただ一方で、どこまで「ダメなところに目をつぶって、いいところだけ見るようにする」べきかどうかが悩ましい作品になっている。二つの意味で本作は悩ましい。一点目は、平和や戦争の国際的なメカニズムに対してあまりにも無知であるように見えてしまうこと。二点目は倫理的にいい・わるいではなく、倫理をめぐる一定以上込み入った議論を単純にご存知ないのだろうな、ということ。
エンタメとしての本作を褒めることには特にためらいはない。いい作品だとは思う。ただ、政治的・倫理的な議論については、ちょっと勘弁してほしいというか、見ていて悩ましい気分になった。本作の政治的/倫理的問題への接近も、半分は単に作品の「味付け」として行われているのだろう。半分本気、半分商売、ぐらいの感覚で。なので、そこを本気でdisるのも、大人げないと言われそうではある…が、大人気なくdisってしまいました。
【本文】
■エンタメ作品としての卓越
とりあえず、マンガとアニメだったら、この作品は断然アニメのほうがいいかと思います。なんか、マンガはどんどんと描写が荒くなっていった感じで、アニメのほうが全体的に絵の作り方といい何といい丁寧で迫力のある作りに仕上げられているところが多い。
まず、一期の感想でも書いたとおり、本作は非常に迫力あるスタイリッシュなガンアクションのアニメとして仕上がっており、そっち系のエンタメ好きの人が楽しんでみるぶんには充分良いできだと思う。
大胆なアングルのとりかたや、カメラの揺らし方、戦闘が急激にはじまり、急激におわるような緩急のとり方。みていて、飽きさせない。
さて、その一方で、いくつか不思議な気分になったポイントも多く、正直、これはちょっとどうしようかな、という気になる部分もかなり多かった。
■「戦争を知らない人間が、知っている戦争」
第一に、不思議な感触がしたのは、基本的に戦争を知らない我々、日本人がミリタリーものをやると情報源が一緒なんだな、ということに気づいてしまうことだ。わたしの読んでいる軍ネタと、本作の作者が読んでいる軍ネタはかぶるだろう。
おそらく、作者が読んでいる戦争の元ネタは例えば次のようなものだ
・ピーター・シンガー/山崎淳訳『戦争請負会社』(日本放送出版協会, 2004年)
・ピーター・シンガー/小林由香利訳『子ども兵の戦争』(日本放送出版協会, 2006年)
・ピーター・シンガー/小林由香利訳『ロボット兵士の戦争』(日本放送出版協会, 2010年)
・アンディ・マクナブ『ブラヴォー・ツー・ゼロ』(早川、1995)
また、 {netabare} 人間爆弾の描写がでてくる話があるが {/netabare}あれは、イラク映画の『ハート・ロッカー』に似たような描写がでてくる。
他にも、ガチの軍オタの人であれば、もっとたくさん元ネタを挙げることができるだろう。わたしが挙げたは有名どころばかりだ。
そして、これが「戦争を知らない」ということなのか、ということを本作をみながら改めて感じた。
我々は、戦争を知らない。だから、「同じ戦争のイメージ」しか作れない。
ヘルシングの少佐の「殲滅戦が好きだ、電撃戦が好きだ、打撃戦が好きだ、防衛戦が好きだ、掃討戦が好きだ撤退戦が好きだ」…ではないが、戦争というのは、一個の社会現象でもあり、「戦闘」の外側に多様な側面をもっている。そして、「戦争を知らない我々」は、その外側の多様さ、を充分にしることがない。
たとえば、「銃後の社会」のリアリティが我々にはあまりない。すなわち、戦争の前線でもなく、兵站(ロジスティックス)でもなく、「戦争をしている国」がどういう社会になっているのか、というリアリティが我々にはない。リアリティがあったとしても、それはほとんど、二次大戦の非常にベタベタといろいろな味付けがされた1940年代の社会の話しか知らない。
あるいは、戦闘と戦闘の間の時間をどのように過ごすか、ということの感覚はまったくわからない。わからないだけでなく、それが戦争映画や、戦争マンガにおいて描かれても、おそらく我々はそれを「退屈だ」と感じる可能性のほうが高い。それが戦争を、知らん、ということなのだ、ということを本作を読みおえて、ふと思った。
ベトナム戦争を描いたキューブリックの映画『フルメタル・ジャケット』やイラク戦争を描いた『ハート・ロッカー』といったアメリカの映画と、日本人の描く戦争モノの違いは、おそらくまずそこにある。
「戦争をしている人びと」の「戦場」の感覚をそのものがどのように立ち現れるものなのか。日本人は、そこをほとんど理解することができない。鬱屈と、ストレスを抱え込む戦場のリアリティを描くことができていたのは、やはり、20世紀中盤の作品で終わってしまう。大岡昇平の『野火』みたいな作品は、現代の日本人は描くことができないし、たとえ描いたとしても日本語圏内では、そのリアリティがうまく伝わらず「売れる」作品にはならない。
たとえば、1997年に売れた妹尾河童の戦時中の記憶をもとにした自伝小説『少年H』は、珍しく戦争、それも銃後モノのヒット作だったわけだが、97年にかかれた「記憶」はあまりにも危うく、戦後52年間の間に変容をとげていた。「戦後になるまで誰も知らなかったはずの事実」をあたかも戦時中に知っていたかのように描かれていたり、おびただしい数の事実誤認や歴史的齟齬がみられる内容だった。(※山中恒による批判)
よくもわるくも戦争を知らない国、というのはそういうことだろうと思う。
「平和ボケ」などというバカ丸出しの言葉を使う気はないが、これが平和であるということなのだな、ということを改めて思う。
わたしは、平和ボケでかまわない、と思うが彼我の差、というのを感じざるには居られない。
■専門用語はどのように「雰囲気」に機能するのか
第二に、本作で連発される軍事系の専門用語だ。PMC(Private Militaly Company 民間軍事会社)や、UAV(Unmanned Aerial Vehicle 無人戦闘機)といった言葉は、ある程度まで軍ネタに詳しい人にとっては驚きに欠ける話である一方、知らない人にとっては何の話だかわかりにくい。こういった用語は一体どのように機能しているのか、不思議な気分になった。非軍オタの人にとっては、ただ単に意味不明なんじゃないかと思った。
ただ、この疑問は比較的すぐに解消。
非軍オタの大半の人にとっては、まあ作品全体の「雰囲気」に貢献するパーツとなっているのだね。
魅力のコアとしてこういう用語を打ち出してくるのでなければ、こういう「わからない言葉」というのは、それなりに機能してしまうものなのだなぁ、ということをしみじみと感じさせてくれる手法だな、としみじみとした。
これが、第一話の一発目じゃなくて、銀英伝みたいな会話ばっかのアニメだというわけでもなくて、あくまでガンアクションと人間ドラマが主体の構成だから、なんとか機能してるんだろう。なるほど、そういうものか、と。
メインディッシュとしては、こういうものは機能しないが、デザートとしては、こういうのって機能するんだよなぁ、としみじみ感じた。
■世界平和は達成されるか。
ここから、核心のネタバレの話である。
{netabare}
さて、そして、本作の主題である「ヨルムンガンド」であるが、これは正直、ちょっと…いや、だいぶがっかりした。
結論から言うと、
「新しい強力な兵器」というものが世界平和をもたらすかっつーと、もたらさない。もたらされるのは、戦争のあり方が変わるという、それだけのことだ。
具体的には、次のような世界史的な知識があれば、容易に推測のつくことだ。
{netabare}
鉄、騎馬、銃、核兵器といった新兵器は、発明されるたびに世界の勢力図を大きく変えた。
しかし、勢力図は大きく変えたが、平和をもたらしたわけではない。
核兵器は、一時的にアメリカ主導の世界平和をつくろうとしたが、一瞬でソ連にパクられ、いまや北朝鮮程度の技術力しかない国家からさえもパクられようとしている技術に成り下がってしまった。
「世界平和のための新兵器」は、新兵器を開発することの難しさ以上に、それを「独占」した状態を保つことが難しい。
・独占を成立させるためのメカニズムをどう作るか。
・あるいは、大量破壊兵器などを使用させないメカニズムをどう作るか。
そっちのほうがたいがいの場合において重要で、そのメカニズムの設計のほうがつらくて、大変なのだ。
世界大戦のような、「損益分岐点がきわめて高い、富裕な、国民国家による戦争」は、二次大戦以後はおこっておらず、そっちの戦争は、ひきがねを抑える仕組みの設計がうまくできれば、そう簡単にはおこらない仕掛けにいまのところなっている。とは、言っても起こってしまうときは起こってしまうのだろうが、そう簡単には、アメリカ vs 中国、みたいな戦争はまず起こらない。世界戦争は起こってしまったときの悲劇は巨大だが、起こる確率そのものは高くないものだ。その点での平和はある程度達成されており、ここをあえて封じるという必要はいまひとつよーわからん。
しかし、いま世界でおこっている戦争の悲劇は、こうした類の戦争ではない。
{/netabare}
{/netabare}
作中では、キャスパーが少し反論として「人間は、石を使ってでも戦うよ」という趣旨のことを発言しているが、キャスパーのほうが正しい…というか、作者は、キャスパーの反論でもってバランスをとったつもりなんだろうが。こんなのは、率直に言って、論争にすら値しない。
{netabare}
現代の…とりわけ、アフリカなどの地域においては、100億円の戦闘機同士が戦う戦争よりも、3000円の自動小銃(カラシニコフ、AK47)での殺し合いによる悲劇のほうがより一掃深刻である。兵器の値段も安ければ、人の命も軽い。そういう場所での悲劇のほうがでかいわけだ。
アフリカや、南米における、いわゆる「失敗した国家」の中での殺し合いを止めることのほうが、2012年現時点における戦争抑止的な目的としては重要で、それは制空権だとか、電子戦を制圧することとは関係ない。電子戦において、最強を誇れれば、そりゃまあ、欧米の軍隊と対峙した場合には極めて有利だとは思う。アメリカ主導ではじまったアフガンやイラクの悲劇を止めるという側面での効果はあるだろうとは思う。すなわち「アメリカ抑止」はできる。だが、アメリカ抑止ができれば、戦争根絶ができるわけではない。
重要なことは、まずAK47を少年少女の手からとりあげることだ。そして、軍隊で戦う意外に能がない人びとに平和的な職業を供給し、社会制度を安定させる。これが重要だ。とても地味でマンガの派手なネタにするのには向いていないが、現代的な「平和活動」とは、まずはそこだろうと思う。(ここらへんは、伊勢崎 賢治『武装解除』あたりを参照)
ご都合主義SF的な設定が許されるにしても、たとえば、
1.AK47以上に、安価で扱いやすく、威力のある汎用兵器をまず普及させる
2.その上で、その兵器のなかに強制停止装置を組み込んでおき、任意に利用を停止させられる仕組みをつくる
とかのほうが、まだもうちょっと説得的である。
*
よって、ヨルムンガンドによって達成されるのは、「世界平和」などでは全くない。
ココが制空権を取得することによって、目指せることがあるとすれば、それは「世界平和」ではなく
・核戦争抑止
・世界大戦の阻止
・大国の軍事力の縮小
といったことではないだろうか。そういうことならば、話はわかる。
制空権を握ることには、ある程度意味はある。
しかしながら、冷戦が終わってしまった現代においては核戦争・世界大戦・大国同士の戦争といったような危機は、現代の主要な危機とは言い辛く、ぶっちゃけたことろ、物語としての緊迫感がぜんぜんないだろう。だから、話の構成自体を大幅に変えて、
世界大戦や、核戦争の危機が迫っているという、前提とする世界設定の構成そのものを、もっと前段階で変えておかないといけない。中東やアフリカの泥沼化した戦争の話は、ざっくりと削除して大きく作品の方向性自体を変えたほうがいい。
■どちらかというと、ヨルムンガンドによって、世界の戦争はより一層ひどい状態になるのでは?(2013/07/26追記)
あと、思ったこととして、ココのやり方だと世界の戦争状況はより一層悪くなると思われました。
アメリカ抑止や、国連軍の行動を抑止するということは、要するに、アフリカ諸国などの紛争地帯における戦争を抑止させるパワーがなくなる、ということです。アメリカ軍を抑止するのはまだしも、国連軍の行動については批判も多いですが、アメリカや国連軍によって、アフリカ等の地域の戦争が一定程度抑止されていたのも事実です。アメリカさんや、国連さんが出てきたら、やはりそれなりに強いので、とりあえず、戦争が止まるという側面もあったわけで、だからこそ「パックス・アメリカーナ(アメリカによって維持されている平和)」という言葉もあるわけです。アメリカが世界の警察を気取ることに対する批判はもちろんあるわけだし、それはしていいし、するべきだとは思うけれども、アメリカが戦争の火種になっていると同時に、平和維持の圧力になっている側面もある。
で、ココのやり方だと、アメリカや国連軍に対する抑止にはなるけれども、アフリカで自動小銃を手にトヨタ車にのって戦っている子どもの兵士たちを抑止することにはビタイチ貢献しないわけだ。そうなるとどうなるか、というと、アフリカや南米などの地域で、戦争をやっている連中がやりたい放題で戦争をしようとしたときに、それを止められなくなるわけだ。アフリカが今よりもさらに激しい「戦国時代」みたいな状況に陥る可能性がある。
それって、世界平和どころか、単なる無秩序といったほうがよい。
■実際的には、アメリカや国連に対する抑止力をもった第三勢力程度のものとして機能するのがいいのでは(2013/07/26追記)
で、も少し、ココの作戦が実効力をもつケースを考えると、やはりあくまでアメリカやOECD諸国の「横暴」に対する抑止力として機能する、というのがメインになるはずなので、たとえばイラク戦争やアフガン戦争のような、アメリカによる非道な戦争を止める。あるいは、核戦争のようなものを行えないようにする、大国同士の戦争抑止力として機能させる、ということ以上にはないと思われる。
アフリカ諸国への国連による紛争停止のための介入措置などには、むしろ干渉しないほうがいいので、こういったものについては「非干渉」を貫くということを声明として発表するのがよかろう、と。
そうなると、やはり、世界中の飛行機を止めるなどという馬鹿なことをやる必要はなく、アメリカや国連に対する監視勢力として有効に機能しうるということをアメリカと国連に対して証明し、国際的に影響力を与えられれば、それで必要十分。そこで、70万人を殺す必要は皆無だし、世界中の制空権を握るためにそんな変なことをやる必要はない。
*
あと、この話の設定上、「「制空権」以外の流通も、HCLI社が握っているから、地上戦が起こった場合は、HCLI社が対応しるんだ。だから問題ない」みたいなことを言うとる人をみかけけれども、それは、ちょっと「市場」というものをわかっていなさすぎる。まあ、フィクションだからね、という話はまああるけど……あるけどもさ……。
また、わたしも読んでないけど、この手のネタをもうちっと真剣にやるなら、
岡田 斗司夫『「世界征服」は可能か? 』 あたりが、一般向けに丁寧に書いているらしいので読むと、たぶん面白いだろう。
本作はそこらへんはザルであることは、著者はどこまでその点に自覚的なのかがわからないので、読んでて不安になる。
最後のほうの展開とか、単に寒々しい。ヨルムンガンド計画のような、あたまのわるい計画の発案・実行者が、ココのような作中における「天才」キャラではなく、もっと馬鹿な悪役系の小物がトライしようとして失敗するというのならば、わかるんだけれどもね。
{/netabare}
ただ、そうは言ったものの、本作は、国際政治論や、軍事史、世界史とかに一家言ある人が読むっつーよりも、明らかに兵器萌え系のミリオタ作品であるので、そこらへんにツッコむのは「ヤボ」と言われれりゃそうなんだろう。あくまで兵器萌えの人びとむけの作品だと割り切ればいいのだろう。
戦略(Strategy)や、外交、戦後復興あたりの話まで含めて多少なりとも知っている人が読むと、がっかりするので、期待してはいけなかった、ということなんだろう。
それにしても、どーせわからないのならば、ヘンにそれっぽく描写しないで、わかんないなりに、もっとバカっぽく済ませていれば、消費者サイドとしても、気にならないのだが。
まあ、それっぽく描くことによって、作品の「雰囲気」を演出してみせているのだから、そこには作者にもジレンマがあったのかもしれない。
もっとも、こういう突っ込みばっかりしていると、「設定厨、乙」と言われそうだけれどもさ。まあ、確かに作品制作の現場において、凝った設定を作りこむよりも、多少の問題があるにせよ、作品を仕上げるためにさっさとネームを仕上げていくことのほうが、重要になる、ということはもちろん理解する。
仕事を成し遂げるというのは、クオリティ、コスト、納期のトレードオフの中で戦うことだというのはもちろん、わかる。
だから、上記のツッコミは、設定厨のツッコミに過ぎない…ということで、別に、他の視聴者が気にならないのなら、気にならないで、それでいいかもしれない。「おれにとって、ヨルムンガンドの魅力は兵器萌えで完結するんだぜー!」という人にケチをつける気は毛頭ない。
だが、次の点は、設定厨うんぬんのレベルではなくて、いろいろとマズい。
{netabare}
■犠牲と秩序
大きな目的の達成のために、相対的に小さな犠牲を出すという話は、いくらでもある。
本作が異色なのは、ココのノリが「比較的さっくりと犠牲を出しちゃおーぜ」ってノリなんだよね。あんまり逡巡しない。逡巡するのはヨナくんぐらいで、「大人はわかるもんだ」というノリ。おいおい、待ってくれ。逡巡すべきは、ヨナじゃない。ココだ。「未熟者」のヨナだけが逡巡し、「天才のココ」が逡巡しないというのは、明らかに製作者による素朴な倫理的世界観を反映しているように見える。
もし、素朴な倫理的世界観ではないのであれば、その構図は、逆だろう、とわたしは思う。
天才こそ、この選択に逡巡してほしい、とわたしは思う。
ココの決断が、「オトナ」からは、何の反論もなく、「オトナの世界観」として提示されているのは、あまりにもゾッとしてしまう。
なぜ、もっと政治的に正統な手続きを踏まずにいきなり、強制力によって飛行機に乗り合わせた70万人を殺していい、という論理になるのか?※1
その場合は、「ある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるか?」というトロッコ問題※2という倫理学上のよく知られた難問としての性質を帯びることになる。
最近、この問題をあらためて有名にしたマイケル・サンデルの紹介から引用しよう
「あなたは路面電車の運転手で、時速六〇マイル(約九六キロメートル)で疾走している。前方を見ると、五人の作業員が工具を手に線路上に立っている。電車を止めようとするのだが、できない。ブレーキがきかないのだ。頭が真っ白になる。五人の作業員をはねれば、全員が死ぬとわかっているからだ(はっきりそうわかっているものとする)。ふと、右側へとそれる待避線が目に入る。そこにも作業員がいる。だが、一人だけだ。路面電車を待避線に向ければ、一人の作業員は死ぬが、五人は助けられることに気付く。どうすべきだろうか?」
このとき、「5人を助ければいいじゃない」でという立場の考え方を、「結果主義 consequentialism」 と呼ぶ。
ココの立場は、この結果主義に属するものだろう。こういう立場の人がいる、ということ自体はごくふつうのことであり、この考え方自体は、トロッコ問題に対するもっとも伝統的で、オーソドックスな立場である。
そして、トロッコ問題が伝統的である…ということはすなわち、この問題に対する反論も、ズラッとある、ということだ。
全部を、順をおって紹介していると、長くなる(※3)が、短くまとめよう。
ココのような立場で、「70万人の犠牲か、1000万人の犠牲か」みたいなことを考える人は、基本的には、こういうトロッコ問題のような状況を思考のモデルとして採用しがちだ。それは、戦争を延々とドンパチとやっていて、作戦指揮官のような立場にいる人だと、そういう価値観になりやすいのは仕方ないところもあって、人の命をソロバンではじくような慣習のある場所では、こういう感覚は、通りやすいだろう。「いま、撤退を決めなければ、さらに100人が余計に死ぬ!」とか、「あの2人を助けようと思ったら、5人~10人の兵士が犠牲になるだろう」とか、考えながら戦闘というのはやるわけだから、こうした命のソロバン勘定にはなりやすい。こういう立場の人がいること自体は重要だし、こういう信念をもった世界観の人が、意義のある立場を担うことは実際にたくさんあるだろう。(※4)
だが、それは前提が間違っているのである。
ココが選択できる状況は、トロッコ問題のような構造をとっていない(※5)。
トロッコ問題は、選択をするための時間が短く、交渉の余地がない。戦闘での作戦行動中も、しばしば選択するための時間がない。しかし、ココは、その気になればアメリカやロシアを相手取ってテロリストとして交渉する時間が残されている。
しかしながら、ココは(おそらく)戦闘行為中における「7人の犠牲か、100人の犠牲か」といったことの、単純な延長として、この問題を考えてしまっている。それは、端的に言って間違いだ。しかしながら、人は、多くの場合、何か一つの、「モデルとなるケース」をベースにしてものを考えてしまいがちだ。
「7人を守るか、100人を守るか」を、1分間の間に判断しなければ全てが台無しになってしまうような場では、確かに、単純に人数の大小を比べてもいいかもしれない。しかし、交渉の余地がじゅうぶんある中で、「70万人を殺すか、1000万人が結果的に死ぬか」という選択肢だけ考えてで、「交渉をする努力をする」という努力をしないことは、選択の構造そのものが大きく間違っている。
しかし、ココは「7人か、100人か」という選択肢が、ごく当然の問題構造であるかのように振る舞う。はっきり言って、それは「平和ボケ」のまるきり逆のパターン。「戦闘ボケ」そのものだ。戦闘の感覚<だけ>で、ほかの様々なケースが判断できる、という立場だろう、それは。
戦闘に浸かって生きてきた人間は、戦闘の感覚で解決できる問題は、それでいい、と考えがちだ。
シュンペーターによれば、そのような感覚こそが、戦争抑止が失敗するもっとも典型的な理由の一つなのだ。(※6)
「犠牲」が必要ないとは言わないが、「犠牲」の出し方を選べるのならば、選ぶべきであり、可能な限り努力をしなければ、結局、そのような悲劇を生んだことは、のちの歴史までずっと、社会の摩擦として残り続ける。
近代は、こうした、大量の「戦闘ボケ」によって、「大きな目的のための小さな犠牲」を許してきてしまった歴史でもある。それは血塗られた歴史、として残り、いまでもたくさんの紛争の火種としてくすぶり続けてきた。
「犠牲」が必要ないとは言わないが、「犠牲」の出し方を選べるのならば、選ぶべきであり、可能な限り努力をしなければ、結局、そのような悲劇を生んだことは、のちの歴史までずっと、社会の摩擦として残り続け、後の歴史や、社会の規範そのもののありようを変えてしまう。犠牲を出す以外の選択が明らかに筋が悪いのであれば、それもやむを得ないという判断はありうるだろう。犠牲を出すという選択と、出さないという選択の間で、強烈に悩んだうえで、あえて犠牲を出すことを選択するのであれば、それが支持できるかどうか……は最後までわからないが、少なくともそのときには、ココの判断に安易に批判を加えることはできない。※7
「最終的に結果が正しければいい」という発想は、むろん一理ある発想なのだが、その結果にたどりつくまでのプロセス自体が、のちの世界の動乱のタネになりうる。それは、政治について考える人間にとっては、もはや常識なのだが、<結果とプロセス>を完全に切り離して考えられると思うのも、モデルの間違いである。そのモデルの間違いは、小さな問題であれば、影響が少ないこともあるだろう。しかし、「世界平和」のような大きな問題になれば、そのモデルの間違いは、大きな結果として響いてくる。※8
{/netabare}
そういうわけで、本作は戦闘描写のほかには何も期待できない。
作者は、明らかに「戦争」についてわかっておらず、「戦闘」と「兵器」のことしか考える能力がないように見える。
まあこういうボケをかます作品がさらっと出てこれるという寒々しさが、今の日本なのか。やばいな、と。ガチのミリオタ諸君は、こういうヌルいミリオタに対して批判を加えることで、ミリオタの水準をぜひ提示していただきたいと思う限りです。ミリオタなら、こんな作品を褒めてはいけない…!そう思うわけです。(わたしはミリオタじゃないけれども)
なお、戦争抑止の話にせよ、民主主義の話にせよ、新しい科学技術の話にせよ、いずれも偉大なるシュンペーター大先生の守備範囲なので、この著者は、シュンペーターの話をひと通り読むとすげー感動するんじゃないだろうか。
※1 ただ、これ、ほんとは、設定厨的に言わせてもらうと、20世紀では、年間の戦争犠牲者は100万人~200万人(『word military and social expenditures』より)。これは二次大戦も含んだ20世紀全体の平均なので、戦間期であれば実際にはもっと少ない。とりあえず、単純に月あたりで割り算すれば8万人~16万人程度。ココは、「70万人位が犠牲になる」と言っているが、戦争でそれだけの人数が死ぬのは、4ヶ月~9ヶ月はかかる。大きな戦争がまったく起こっていない時期の慢性的な戦争状態での、犠牲者はそれよりもはるかに少ない。時期によっては3年~4年ぐらいかけてようやく、70万人の死者数だろう。
…で、そんなに時間的な余裕があるなら、いきなり飛行機を落とすような強制的な手段をとらずとも、テロリストとして国際交渉すればいいわけで。もっとはるかに犠牲が少なくて済むはず。…なので、「大きな目的のために、小さな犠牲」ではなくて、これだと「大きな目的のために、大きな犠牲を出す」という、素朴な功利主義的立場をとるとしても、費用対効果の悪い選択であって、単に愚策だとしか思わないのだが……
まあ、でもそれも、設定厨の発言だということで譲歩するとしよう。
たぶん、この作品世界では、毎月500万人ぐらい死んでいるという設定だとしましょう。そういうつもりで、上記の文章は書いています。そうじゃないとはなしにならないので。
※2 サンデルは、この問題を、古典倫理学の典型的区分とからめて紹介しているが、ダブル・エフェクト原理、消極的義務/積極的義務、神経倫理学などのさまざまな議論の広がりがみられる、非常に大きな話である。
※3
反論の一つは、「行為の結果ではなく、行為者の意図こそが問題になる」という立場。(意図主義/ダブル・エフェクト原理)。犠牲者を明確に殺すつもりでやったのならば問題があるが、犠牲者を殺すつもりがあったのでないならばそれは問題ない。という立場だこの立場は、カトリック教会の立場でもある。この立場にたつと、たとえば妊娠中の胎児を殺すことは「明確な意図をもった殺害」なので、だめだ、ということになる。
こうした立場をさらに発展させて、「1人の犠牲か、5人の犠牲か」ではなく、「1人を積極的に殺すか、5人を守る」という選択で悩んでいるのか。「1人を守るか、5人を守るか」で悩むのとでは、そもそも意味が違う、という議論が出てくる(ジョン・ウィリアム・サーモンド『Jurisprudence』)
さらに、神経倫理学の話は、スティーブン・ピンカーのベストセラー『心は空白の石版か?』でも触れられている。
※4
トロッコ問題は、功利主義の問題だが、
経済学を習った人であれば、即座に「サンクコスト」のことを考えただろう。
※5
この批判の仕方も、倫理学におけるよくある批判で、サンデル自身が、「ロールズの正義論」という、非常に有名な議論を使った論法である。
※6
正確には、シュンペーターの主張の文脈はけっこう違うのだが、「戦闘を生業としてきた人間の選択構造こそが、戦争を継続させ続ける」というのは大枠でいえば、いっしょだということで。
※7 このへんの、「大きなことをなすためにいくらかの犠牲を出すこと」に対する是々非々は、コードギアスのところにもちょっと書いた。細かい理屈をより知りたい方は、コードギアスの場合はルルーシュとスザクの対立として、も少し発展的に書いたので、興味と暇のある人はそちら読んでいただきたい。
※8 むろん、こういった倫理的なツッコミを作品についてしていると、文芸批評理論をかじった人であれば、私に対して「作品の価値を、道徳的規範から批判して判断する、というの批評の立場だとは言えない」というだろう。昔、このことで、さる文学畑の人から、「ありえないほど馬鹿」呼ばわりされたのでw、防衛的なだけのコメントをしておく。
それは、確かにその通りで、作品の芸術的価値、あるいは娯楽としての価値と、倫理的価値/道徳的価値は、相互に独立した価値として論じることができる。それはあたりまえのことだ。
だが、こういうことを言うと、文芸界隈の人には、かなり叱られるかもしれないが、文芸批評理論は、あくまで文芸批評理論のようなものを考える「多様な読み」の可能性とかを考えるタイプの人たちの間で流通するものに過ぎない、と側面もある、とわたしは思っている。はっきりと言って、DQNの人たちの文学受容とか、そこらにいるアニヲタの作品受容と、文芸批評理論は別のものだと思っている。文芸批評理論のひとたちは、倫理的価値とは関係のない、芸術的価値という独立した部分を論じてればいい。
だから、わたしは、『ヨルムンガンド』の倫理的価値が、『ヨルムンガンド』の芸術的価値にダイレクトに影響するという立場をどうしてもとりたいなどということを考えているわけではないし、ヨルムンガンドが独立して芸術的価値をもっていると考えている人は、それを倫理的価値と断絶して論じればそれでいい。そのことについて、私はツッこまない。価値は独立しているのだから、別々に論じましょう。それでいい。
それでも、倫理的立場からのコメント自体が、規範的にありえないと思う人は次の二つの問題を考えて欲しい。
一つは、作品のもっている文学性と政治性の関係だ。文学作品にはしばしば、政治的メッセージをもったものがある。そして、それは実際に文学の形をした政治的メッセージとして消費される。たとえばプロレタリア文学だとか、島崎藤村の『破壊』だとか、そういったものだ。こういったものは、ごく特定の政治的文脈において、ほとんど政治的メッセージそのものとして発せられる場合がある。たとえば、『A』の森達也は、マイケル・ムーアのことを批判している。なぜかと言えば、マイケル・ムーアのドキュメンタリー作品は、あれはもうドキュメンタリー作品である必要はなく、単に政治的メッセージに近いものだからだ、というのが批判の趣旨だ。まー要するに小林よしのりの『ゴーマニズム宣言』は漫画作品なのか、政治的論説なのか、という論争に近い。少なくとも小林よしのりの『ゴーマニズム宣言』について「あれは、単に作品なのだから、小林の主張の政治的/倫理的問題について論争するのは、作品批評としておかしい」とか誰も言わないだろう。『ゴーマニズム宣言』は明らかに、政治的論説そのものに近い(むろん、その中でも多様な読みを可能にする作品としての性質<も>見出すことはできる)。マイケル・ムーアのドキュメンタリーと比較した場合、『A』は読みの多様性、というか、「このような現実もあるのか…!」ということを携えているだけで直接の政治的メッセージを協力に発揮しているわけではない。文学作品なのか、政治的論説なのか。その区分は線引があいまいであり、文学作品は政治的論説としての機能ももつし、それは受け手や、状況によって変わるわけだ。
第二に、その上で、ブルデューが『ディスタンクシオン』において明らかにしたような、社会階層によって趣味の受容やリテラシーが変わる、という問題などを考えてみてほしい。元暴走族教師のマンガ『GTO』における、鬼塚の発言を、DQNの読者はどのように受け取っているだろうか?武田鉄矢の『金八先生』のセリフを、みつを好きのおっさんが観た時の受容はどのようなものだろうか?ぶっちゃけ、そこらのアニヲタとか、DQNとか、文芸批評理論的な前提を共有しない数多くの読者は、作品のもっている政治的機能、世界観を、<多様さに開かれたテクスト>としてではなく、<一意のメッセージ>として受け取る可能性をつよくもっている。極端なことを言うと、<テクストとして読む>という態度を徹底させれば、北朝鮮のプロバガンダ映画だって、テクストとして読める。しかし、北朝鮮のプロパガンダ映画は、明らかにそういうものとして流通しているわけではない。
ってか、少なくとも、本文のなかで、わたしはヨルムンガンドの作者の描写を、<テクスト>としてではなく<メッセージ>として、乱暴に同定してしまっている。しかも意図主義の立場(倫理学の意図主義ではなくて、美学概念としての「作者の意図主義」)をとって。
この『ヨルムンガンド』を、徹底して<テクスト>と読むのであれば、わたしのような言い方にはならないだろうとは思う。しかし、わたしは、勝手に本作の作者を、戦闘ボケだとなじり、ココの解決策を批判しているのは、この作品が<テクスト>として機能するよりも、<メッセージ>として機能する可能性が大きいと考えるからだ。
そのような作品受容を想定するからこそ、わたしの倫理的判断からの批判は行われている。
わたしが「倫理的判断」を持ち出すことが「そもそもテクスト論的にありえない」というのならば、その通りだ。だって、わたしは、ここでは「テクスト論的な立場とは、違う立場から論じる必要性がある」という判断をしているのだから。
だから、もし、わたしの倫理的判断という行為そのものをdisるのであれば、「そのようなメッセージとして受け取るような、リテラシーのない馬鹿はいない。」と言うのであれば、わたしは納得する。

4.8