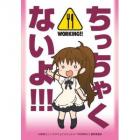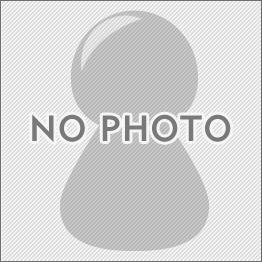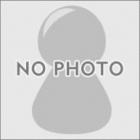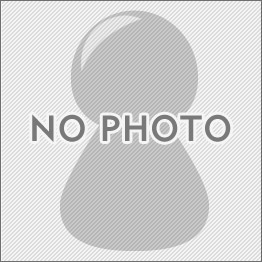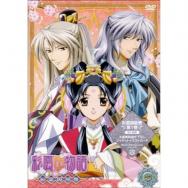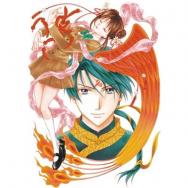薄雪草 さんの感想・評価
4.4
物語 : 4.5
作画 : 4.5
声優 : 4.5
音楽 : 4.5
キャラ : 4.0
状態:観終わった
しっとり、楽しめました。
3話まで視聴しましたが、とても良い印象です。
今のところ、1~2話のオムニバス形式ですので、コンパクトで観やすく、それでいて人の機微の深奥を滲ませる雰囲気にも惹かれます。
お話のコンセプトは、烏妃(うひ)と呼ばれる妃 ≒ 巫女が "招魂の術" を駆使し、生者の情念と死者の所思とを邂逅させるというもの。
遺された人と楽土へと旅立つ者の双方を取り持ち、魂の安寧を施す人情綺譚物ともいえそうです。
触れれば消えてしまいそうな "粒よりさ" がすこぶる魅力的な本作ですが、片方では、帝国内の権謀術数、後宮の怨嗟憤懣がうずまく宮廷怪奇譚とも読み取れそうです。
でも、もしかしたら、もう少し壮大な時空のスケールを見せてくれるのではないかと期待できそうなエッセンスも感じています。
~ ~ ~
1~3話。
{netabare}
これまでのストーリーから読み取れることをいくつか。
一つめは、烏妃≒柳 寿雪(りゅう・じゅせつ)の名前に、深い謂れがあるように感じます。
まず、烏妃とは、代々の役務上の呼び名のようです。
日本でしたら武内宿禰でしょうか。
だって彼の寿命は、280~360才と言われていますから。
幼かったときの寿雪には、元の姓の記憶がありません。
彼女のそれは、先代・烏妃の意図的な改名のようです。
このあたりのくだりは、紀元前200年頃の中国に伝わる「楚漢争覇」に一つのモチーフが見つけられます。
二つめは、OPに描かれる人面の怪鳥(烏漣娘娘・うれんにゃんにゃん)と、金羽の鶏(星星・しんしん)という化鳥の存在です。
信仰の対象として、鳥を崇める風習は古代ギリシアのころに遡ります。
なかでもカラスなどは、世界的に見ても "太陽の化身" とも目されています。
国の運営は、太陽の恵みをあまねく地上に下ろす人のわざに外なりません。
その舵取りのためのメッセンジャーという役割りが、太陽の使者であるカラスであり、この物語の烏妃なのですね。
三つめは、寿雪の銀髪です。
彼女の髪は、西方アジア文化圏の民族(今のウイグル自治区あたり)の歴史性、現代史性を象徴させています。
あるいは遠くギリシア文化圏に及ぶ立ち位置、それは民主主義への歴史観だったり、尊い人間の精神性だったりを彷彿とさせています。
(たしか2020年、アメリカで、新疆ウイグル自治区から、かつらや付け毛=人毛?などの毛髪製品13トンが輸入された記事があったような気がします。)
そう思うと、寿雪の墨髪も、深い顔立ちも、どこか抑圧された翳りが、彫塗されているように見えてきます。
また、彼女は、西方と東方との文化を繋ぐ黒子的な役割を担わされ、架け橋となるべくする "大きな意志" を感じたりもします。
四つめは、牡丹の花を自在に扱う術です。
牡丹の原産地は、現在の中国北西部と言われています。
もしかしたら、その土地代々に伝わる特異な秘術のようなものが存在しているのかもしれませんね。
そんな想像が広がると、かの地の風土や人々の暮らしの中に根付いている世界観に興味がわいてきます。
そして、人の願いと花の精とのかぐわしいシンパシーだったり、ささやかなシンフォニーにも思いがはせそうです。
~ ~ ~
何代にもわたって時の皇帝に仕え、たびごとに世上の無常にまみえ、なにごとも人情に流されないことを是とする烏妃。
後宮の妃でありながら、皇帝とは相容れぬものであり、夜伽などもってのほか。
同族を皆殺しにされ、母をも斬首されても、自らを責める気位が彼女の才覚です。
それゆえか、スルースキルがいくらか四角四面に見えるのが玉に瑕のようにも。
でも、弱者への振る舞いは、むしろ慈愛と博愛に満ちているのがうかがい知れます。
ところで、物語は、若き皇帝との夜伽噺にしか見えないのはどうしてでしょう。
ピロートークならぬ、浮世の花水木をしっかり根に下ろしているように見えるのですが。
霊術の微かな施しだけを柱とする物語でしたら、若き皇帝など微塵にも不要なのでしょう。
でも「翡翠の耳飾り(前後編)」で暗喩されてあったのは、忍耐と道徳の二つを "一つとする愛の高貴さ" でした。
なれば、幽玄にも現世にも耳をそばだてることが、寿雪と皇帝(夏 高峻、か・こうしゅん)のお作法になってしまったのですね。
ましてや、夜の水浴みに髪の秘密を見あってしまったとあれば、寿雪は夜伽もむげには断れず、高峻も止められるものではないでしょうね。
~ ~ ~
高峻には、いつもにべもない口上の寿雪ですが、なにぶんとオヤツには目がありません。
なんなく手懐けられる隙の甘さ、緩さは、16才の女の子のままです。
ですが、本来、烏妃とは、漆黒の衣装に本分を秘匿し、政(まつりごと)にも影響を及ぼす妖術使いです。
老獪な先代に仕込まれた数々の秘計が証するものは、おそらくは国の行く末、世界の大事にもさわる苦心苦難の路なのではないでしょうか。
そんな二人が手掛けるのは、真夏の太陽に真白き雪を降らすような陰陽白墨の物語。
今後、いかなる金糸銀糸の錦文様を織り上げていくのでしょうか。
原作は読んでいませんので詳細は分かりませんが、噂によると壮大な世界観が随所に見受けられるようです。
なれば、今回の宮廷奇想譚はその序章にすぎないのかも知れません。
原作にも興味津々ですが、いましばらくはアニメを楽しむことといたします。
次回は「雲雀公主=ひばり姫」。
楽しみです。
{/netabare}
4話。
{netabare}
今回は、ひばり=小さきもの、をテーマに、わずかな読み違え、ブルーなすれ違い、もやもやな衝突、ささやかな心配り、そしてほんのりとした邂逅までが描かれてあったと思います。
ストーリーを追えば、途切れそうな絆の糸がようやくに手繰られ、縁(えにし)の広がりと深まりがゆるやかに紡がれていく様子が感じられました。
しかしながら、それは同時に、「独りで生きていく」と教え込まれた寿雪にとっては、本当に望ましいことなのかどうか、物語は微かに揺らぎを与えています。
ただ、「小さな」贈り物が、どのような想いで手向けられ、どう受け止められると嬉しいものなのかを、優しい演出で表現されてあったことは確かなようでした。
雲雀は、雲へと届かんばかりに空高く昇っては、雀(すずめ)ほどのサイズに見えることから当てられた漢字です。
ツバメは、土喰黒女(ツバクラメ)が語源ですが、巣作りに土を食み、地を這うように飛ぶのが特徴です。
高峻が彫ったアナツバメは、寿雪の術によって霊的な先達と化身し、現世に幽鬼と残された雲雀の未練を断ち切るべく天へと高く飛び上がります。
このくだりは、耳飾り、花笛のエピソードとは少し違っていて、二人の初めての共同作業。
想いを積み重ね、共有しあい、小さな願いをまた一つ成就させたのですね。
雲雀は春告げ鳥とも言われますし、ツバメは春に巣づくりをします。
となれば、今回は、寿雪と高峻の「小さな春」をさえずりあったお話なのかも。
そんな隠れテーマがあったようにも感じました。
神は天から地に降り下って人を救うのですし、帝は地に立って国を治め人を幸せにするのです。
もしもその仲立ちをするのが烏妃の役目であるなら、かえってバランスを崩しかねないのが今回の寿雪の振る舞いなのかもしれません。
ちいさな春を過ぎやれば、物語はいよいよ夏へと向かいます。
次回は「懐刀(ふところがたな)」。
楽しみです。
{/netabare}
5話。
{netabare}
お話としては6話の前ふりでしょうか。
トピックスの一つめは、衛青(えいせい・高峻の侍史)を通じて、寿雪がまた一つ、現世にしがらみを作ってしまいます。
それは、おそらく「謙譲」と呼べるものでしょう・・・。
~ ~ ~
衛青は、高峻の懐刀。
寿雪は、烏漣娘娘(うれんにゃんにゃん)の巫女。
帝と神の違いはあっても、ともに傅(かしず)く者として、それぞれの矜持があります。
寿雪は、後宮の仕来たりに疎く、宮女の話を鵜吞みにしたり、思いもなしに靡(なび)いたり、勘違いもします。
それは、烏妃ならではの隠遁生活に因るものですが、でも、どういうわけなのか、彼女は自らを遜(へりくだ)らせ、謙譲のふるまいもできるのです。
衛青はというと、人には言えない出自を自己の懐に抱えていて、同時に、高峻に見出された恩を胸にしまっています。
彼は、高峻のプライベートな案件で「寿雪を頼りにしない」という命を受けながら、"彼女を頼りにする" というねじれたシークエンスに、自らを内省します。
高峻からの仁と愛、高峻への忠と孝のはざまに立ち、正規の妃ではない烏妃に対して、どのように接するべきか思いあぐねているようです。
でも、高峻を救えるのは寿雪だけであろうことを頭から否定できません。
なぜなら、母を救えなかったかつての弱い自分がフラッシュバックするたびに、強い自分でありたいとの意志が湧き上がるからです。
衛青の矜持は、皇帝の大局をサポートする侍史としての立場と行動にあります。
それに徹することで、高峻への恩義、烏妃への謙譲に対峙し、自らの真摯を証明しようとするのですね。
~ ~ ~
もとより過去の自分に一線を引き、それぞれに立場を得るに至った衛青と烏妃。
彼らには、奉仕者という共通する土台が各々にあり、奉仕する対象が別々にあります。
それゆえに、共鳴する思いを通わせながら、交錯しながらもあえて謙譲に務め、高峻への新たな柵(しがらみ)を編みだすのでしょう。
たしかに衛青の寿雪への謙譲は、高峻への深憂に則ってはいます。
けれども、いつか高峻への忠義に触れる後悔を生むだろうとも腐心しています。
「帝と烏妃とは相いれぬもの」。
高峻が、寿雪の魅力に惹かれながらも、烏妃の秘密に迫ろうとするなら、双方の立場を危うくさせ、やがて発火する局面が訪れることを衛青は杞憂しているのです。
~ ~ ~
トピックスの二つめは、最終パートで、壁掛けの地図に驚く表情を見せていた寿雪です。
本来、地図というものは、国の最高機密であり、世界概念をしばる秘中の秘。
もしかしたら、寿雪は高峻に「地図を見せられた」のかも知れません。
それを共有することは・・・如何なる予想をも超えてきます。
謙譲。
万事に遜り、分をわきまえる行為。
自分を慎み、人を先に立てるマナー。
わりかた簡単そうで、はなはだ難しい美徳です。
次回は「夏の王、冬の王」。
楽しみです。
{/netabare}
6話。
{netabare}
今回は「烏妃と帝とは相容れないもの」の "理由" が明らかになりました。
寿雪の覚悟献身と、高峻の挙動俗心の温度差があらわになり、歴史と未来に亘(わた)る本分において、あからさまに対峙しあったお話です。
律令格式を掌(つかさど)るのが帝なら、祭祀祭礼を司るのが巫女。
高峻は、治世の断行なら私怨にも平然とし、地上に生者の楽世を創出します。
寿雪は、浮世の無常よりも神契にかしづき、死者の魂を楽土へと霊送します。
それならば、帝が仕切るプロセスに生じる敗者・亡者の悲哀業腹を、烏妃が鎮魂にフォローする仕組み、とも解釈できそうな雰囲気です。
とは言っても、寿雪にしてみれば、冬の王として、一生涯を独り後宮に捧げる挺身と、夏の王の治世を支える諦念にほかなりません。
それは、国の泰平のため、世人の安寧のために、選ばざるを得ない栴檀(せんだん)の苦渋でもあるのですね。
おそらくは、それが烏漣娘娘(うれんにゃんにゃん)の意思であり、寿雪への意志ということになるのでしょう。
寿雪が祭祀王として振る舞う以上、そこに自己の実現を差し込む余地はないというわけです。
~ ~ ~ ~
思うに、幼い寿雪には、クーデターのあおりを受けて、母との一別に哭くことも許されず、その生首に心を砕かれた過去があります。
ですが、それすらも抑え込んで、前王朝にも現王朝にも憤怒の責めをいだくことなく、粛々と烏妃を務めています。
果たしてこれほどに過重で過酷な生き方が、なまじの人間に耐えられるものでしょうか。
もしもそんな重圧を凌ぐほどの素養が寿雪にあるとするなら、烏漣娘娘が射止める烏妃の意義とはいったい・・・。
千年の史実からの教訓と、未来の平和へのシナリオの担保になるのが烏妃のそれならば、むしろ「烏妃=寿雪が望めばすべてが得られる」とは如何なる意味なのでしょう。
ここにきて、さらにシナリオが幾重にも織られ始めました。
今回は、香薔(こうしょう:初代烏妃)、蘭夕(らんゆう:夜明宮を造営した帝)、明珠公主(めいじゅこうしゅ:柳下の幽鬼)など、いわくありげな人物や、思わせぶりなパーツ・言質もあちらこちらに見え隠れしてきています。
次回は、「玻璃(はり)に祈る」。
いよいよ楽しみです。
{/netabare}
7話。
{netabare}
玻璃とは、ガラス、あるいは水晶を意味しますが、それを櫛ともすれば、なおいっそう高貴な品物として珍重されます。
若い恋路に祝言の誓約として交わしたそれは、どれほどセンシティブに扱っても、途切れぬ信と愛とを込めたくなるものと窺えそうです。
明珠公主が、死してなお楽土に赴かず、ましてや地縛霊として柳の下に佇んでいたのは、契りへの操を自ら断ち切った未練でしょうか。
決まって春に見せる幽鬼の姿も、誓約の証がいつか掘り出される期待と、永遠に掘り出されぬ哀しみとも言えそうです。
まるで、シェイクスピアのロミオとジュリエットにも劣らない悲恋・悲愛を彷彿とさせるお話です。
それにしても、寿雪の霊力の凄まじさは、巫術師(ふじゅつし)のそれをはるかに凌ぎます。
烏漣娘娘から付託された冬の王たる霊威は、人智を超えたパワーと改めて認識しました。
~ ~ ~
後半は、殺さずの重誓と、茶飲み友だちを申し出る高峻と寿雪とのティータイム。
ひとり重責を担ってきた歴代の烏妃に、傅(かしづ)いて礼を奏上する夏の王の "おもてなし" です。
寿雪のまなじりに浮かんだ涙は、かつての王たちとの和解に至ったからでしょうか。
それとも、先代烏妃の孤高脱俗の労苦が報われたと安堵した気持ちからでしょうか。
寿雪の不愛想の理由は、高峻や世人への柵(しがらみ)が煩わしいのではなく、烏漣娘娘に見定められたいらだちと、冬の王に課されたストレスにありました。
ですから、高峻が、律令の手枷(てかせ)を明々と外しても、烏漣娘娘の爪は、寿雪を暗々と足枷にしつづけます。
どうしたって、寿雪は一介の町娘なのです。
ささやかな恋をし、家を斉(ととの)え、やがては子どもを設け、優しい母となる夢を見ていたのでは?・・・
なれば、烏漣娘々が求める治国平天下という重いテーゼは、烏妃としての日々に何をもって慰めとすれば良いのでしょう。
若き王からの "ティーパートナー" の申し出は、わずかながらも寿雪の肩をほぐし、口を滑らかにするのかもしれません。
王朝は、世襲であっても、征服であっても、所詮は人間の都合で成り立つ治国に過ぎません。
でも、神の意向が天上天下の和平に及ぼすと飲み込める二人だからこそ、夏の王、冬の王として向き合う茶席も「また楽しからずや」なのでしょう。
互いの立場の違いを同じくできる友のカタチとは、「馬鹿もの」と呼び合うのが最も相応しいのかもしれませんね。
次回は、「青燕」。
風雲は急を告げるのでしょうか。
ますます楽しみです。
{/netabare}
8話。
{netabare}
青燕にまつわる、ちょっと切なくて、どことなく理不尽を感じるお話でした。
キーワードは、 "無体" でしょうか。
ときに若さや幼さからの懸想には、往々にして実直に過ぎるアクシデントが生じやすいもの。
たとえその相手が、生者であっても、今は亡き人であっても、真実の愛おしさであったなら、なお一層に世事に縛られず、弁(わきま)えも忘れて、会いたい、逢いたいよと、心は砕かれるものでしょう。
前回、"友との仲直り" への心遣いを説いた高峻が、今回は "寿雪への心通(しんつう)" に一歩足を踏みいれました。
皇太后の呪詛から身を守るためとは言え、微笑む実母と育ての友たる面影との別れを、高峻はどう受け止め、寿雪を評価したのでしょう。
いよいよ夏の王と冬の王の間を詰めたいとの願望をアツく語りながら、烏妃の役務にも愛情があって然るべきと切と唱えたのです。
そうは言われても、寿雪は「難しいことを言う。」と眉をひそませます。
それは、明日の筋書きというものは、何を以って正しく、誰にとって正しいのか、人間の浅ましさや悪(わろ)かしさなどの "無体" からは、何も分かろうはずもないと思うからでしょう。
寿雪にすれば、皇帝・高峻であっても、そのように評定をするほどですから、烏妃にアプローチをかけるには、誰にとっても手こずることでしょう。
ですが、この手こずりは、烏妃の視点に純然と寄り添うのでしたら、意味がまったく反転してきます。
つまり、酷薄な宦官制度という無体、隔絶された後宮という無体には、人間性を虐げる無言の圧となるヒエラルキーが潜在し、個人の生きざまをきつく縛っている "無体の実体" であることにほかならないのですね。
なによりも烏妃に選ばれた我が身の無体がそうなのも、間違いないでしょう。
~ ~ ~
国の安泰を主眼優先とするのが烏妃の立場なわけですので、招魂の秘術は大局の見地に立った局面であやつるのが本来の寿雪のはず。
であれば、彼女は夜明宮でひとり烏漣娘娘と対話を重ね、楽土を地上に降ろす影役(かげやく)に徹する必然性があります。
ところが、彼女は宦官の処遇に施しを当て、衣斯哈(いしは)、恩蛍(おんけい)、衛青らの心のとげを抜き、むしろ強烈な敬虔の念を抱かせるに至ります。
それは、実のところ、夏の王の治世にいささかでも関わることになるし、冬の王としての領分を超えてしまうという矛盾を孕みます。
それ故に、烏漣娘娘が定めた法理に鑑みれば、"愛だの友などの俗世の価値観" を紐づけたい彼らの言上や奏上は、それこそ "難しいこと" と言わざるを得ない寿雪なのですね。
でも・・・だからでしょうか。
恩蛍の肩にそっと手をやる寿雪の作法に、現世の無体を共にしている哀しみの共感と、やさしげな忠恕(ちゅうじょ)の慮りを感じ取ってしまいます。
~ ~ ~
青燕と訊けば、わたしは "幸せの青い鳥" を答えに想います。
それは、若い友への心遣いの先に置くべき、誠実でまっすぐな視界を高くさせます。
望ましさに至る紆余曲折に、心を省み、慎み、そして尽くすからこそ、青い空へと飛翔する姿に、エールが送れるものでしょう。
その尾羽は、小さくて軽いものにすぎないのかもしれません。
ですけれど、人の心を誠心誠意へと感化させるには、あまりに鮮やかな青を失ってはいませんでした。
また、本作は中華圏を彷彿とさせるファンタジー設定です。
けれども、広大な大陸を舞台とはしておらず、洋々とした海洋国家が地図に描かれてありましたから、日本的な情緒性に秀でているようにも感じます。
それゆえに、ひとり一人の幸せの追求は、いずれの国とも違わぬ、あまねく価値観を包摂するものとの作風を期待しています。
今後、寿雪が高峻に求めた木製の薔薇や、百合のお香を醸すベールの持ち主、あるいは7話に姿を見せた新たな巫術師らが、これからの展開に妙味を足してくれそうな気配・・・。
次回は、「水の聲」です。
とっても楽しみです。
{/netabare}
9話。
{netabare}
今回は、今までの流れとはちょっと違っていて、とある宮女のお話が差し込まれていました。
端的に言えば、「死人に口なし」をいいことに、自分の無粋蒙昧を棚に上げた自己中心なキャラを描いています。
寿雪からしてみれば、浅慮や傲慢、屁理屈なわけですが、他の宮女からも "ヘンな人" と取り付く島もなし。友だちもいないそうです。
巷(ちまた)には、「○○は死ななきゃ治らない」なんて酷い言いようがありますが、死んだことにも気づかずともなれば、魂の救いようもありません。
寿雪ができることは「当人が気づくきっかけを作ること」だけ。
「水が救ってくれるやも知れぬ。」とは、言い得て妙だと感じました。
水は穢れを清浄化するほかに、知識、柔軟、変化という象意があるんですね。
今回のエピソードが、大局にどんなふうに紐づけられるのかはまだ分かりません。
「結界が切られた。」と呟く寿雪でしたので、伏線の先の展開に期待が高まります。
~ ~ ~
薔薇の彫刻を届けることに成功した高峻ですが、好いた人が望んだものをプレゼントする嬉しさはきっと一入でしょう。
これがきっかけになって、再び熱をあげることになっちゃうのも、観ている方はワクワクなんですけれど・・・。
とは言え、寿雪の高峻への手紙の文字が全然読めませんでした。(汗)
あれれ?と思っているうちに、ささっと場面が変わってしまったので、演出上の思わせぶり?と思っていたら、2度見で日本語字幕が入っていることに気がつきました。(汗々)
なにせ、寿雪のガードは相変わらず堅い(頭も固い?)ものですから、高峻に何をやらかすのかが、毎回楽しみです。
とにかく、王と王とのやり取りですし、国の隆盛・興亡にも関わる大事ごと。
庶民と冬の王のハイブリッドな寿雪ですし、若さも加われば簡単には測りようがありませんね。
ところで、今回、「梟(ふくろう)」なる呼び名を口にした寿雪です。
烏漣娘娘を身に留めるのが烏妃なら、「知恵」を象徴とする梟の存在は、新たな攻防の軸になるのかどうか気にかかります。
前出の宮女のお話も、つまるところ立場上の怨嗟が因果因縁の元になっていましたし、以前にも、巫術師が追放されたというエピソードもありましたので、怨恨の線なのかもしれません。
あまりにオソロシゲな展開は遠慮したいところですが、今になってほっぽり出すのはいかがなものかと、悩ましく思っています。
次回は、「仮面の男」。
ちょっと・・・ドキドキです。
{/netabare}
10話。
{netabare}
メインストーリーは、五弦の琵琶に執着した楽士の魂を救済し、楽土に送るというもの。
禍々しい亡者の登場には思わず腰が抜けてしまいましたが、「それでも魂を救ってやりたいと思うのだ。」と語る寿雪にも面喰いました。
少しでも可能性があれば、"智" を利かせ "情" を厚くして "力" を尽くすのが当たり前とする彼女の決断。
それが烏妃の学問と道理であり、慈愛の実践、至誠を通す道というわけなのでしょうね。
それにしても、必要であれば即決で国宝を燃やしてしまうなんて、衆人にはもはや理解の及ばないパフォーマンスです。
でも、寿雪はそもそも夜伽をしない妃であり、幽鬼の救済と解放がその領分。
ならば、相手が帝であろうと宝物であろうとも、一刀両断にするのは至極当然なわけなのでしょう。
烏妃の能力をなんども目の当たりにし、明察もしている高峻ですから、寿雪への関心もまた、楽士の執着と紙一重と自覚できようもの。
彼の心のざわめきたるや、如何ばかりかと察せられます。
~ ~ ~
寿雪は神に仕え、霊威をもって魂を救う。
高峻は国を興し、権威をもって人民を導く。
表向きは割れ鍋に綴じ蓋のようにも見える二人ですが、本質では似て非なるものです。
しかしそれが烏漣娘娘の意向でもあります。
国の安泰を使命として背負いながら、相見互いの温情を交わしあうほどに、生木を鉈で裂くような非運を誘う恋の様相です。
~ ~ ~
サブストーリーは、患いのような、煩いのような・・・。
一義には、楽士のお話でしたが、実のところは高峻の患いであり、愁いのお話でもありました。
寿雪は、当初から高峻を遠ざけ、「来るな、もう来るな、二度と来るな。」と辛辣でした。
それは彼女が二人の王の歴史を深く信じているからで、理屈抜きで未練を断ち切るしか術がないからです。
いっぽうで、高峻にしてみれば一目惚れした弱みなわけで、どんなに煙たがられても厭わられても、未練ばかりを募らせるのは同情しかありません。
夜伽も叶わず、妃にも寵姫にも褥(しとね)と置けないとは、帝の位にありながら救われない想いにもほどがありますね。
次回は、「布石」です。
ただならぬ雰囲気に、気を揉んでいます。
{/netabare}
11話。
{netabare}
ここに来てようやく起承転結の "転" 。ターニングポイントのようです。
強気一辺倒で振る舞ってきた寿雪が、人前で初めて弱音を吐きました。
「独り後宮で」、「夜伽をしない」と、誰とも交わらず、「さっさと帰れ!この馬鹿者め!」と、むしろ拒絶をよしとするのが烏妃の本分。
なのに、「16才の町娘」と菓子をほおばり、「人に甘えよ」と肩を包まれては、心がほだされてしまうのも仕方のないことですね。
後宮での殺人事件は寿雪の内面に心変わりを引き起こすトリガー。
これまでとは別次元の要素を加えながらお話が回り始めています。
今までの10話は、そのための「布石」。
今回のお話もこれからの「布石」というわけなのでしょう。
置き石を3子先んじても高峻に勝てなかった寿雪です。
よもや手加減となれば、難局を打開するには相当なリスクとなりそうな予感です。
~ ~ ~
それにしても予想が当たってしまいそうなイヤ~な展開です。
「何かを啜(すす)るような音」とか、「人が嚙みついたような歯型」とか、ホント勘弁してほしいのですけれど・・・。
「死んだ人間を生き返らせることはできない。」と寿雪は語りますが、それはつまり禁忌の呪法があることの裏返し。
絶対悪の邪(よこしま)を上回るのが二人の王の務めなら、立ち向かう試練を覚悟と決めねばならないのかもしれません。
国の乱れが人間の情から発することを正史に学んだ二人です。
道理を顧みない想いに病み伏せる三の妃(琴恵瑶、きん・けいよう)に、どのように応えるつもりなのでしょうか。
また、梟なる男、封宵月(ほう・しょうげつ)の奸計は、烏妃の命を狙いとするもの。
寿雪の存在は、巫術師(ふじゅつし)としても抹消すべき天敵ですし、同時に、高峻に対しても師匠を野に排した仇敵なのですね。
ここは、高峻にとっても一大事。
漢を上げるシーンを期待したいところです。
次回は、「兄妹」です。
どうなる! どうなるの??
{/netabare}
12話。
{netabare}
兄への憧れと過分な期待とが、琴恵瑤(きん・けいよう、三の妃)の異常な執着に形を変え、悲惨な幕切れに至ったやるせなさを強く感じるお話でした。
実のところ、恵瑶の単線思考による自業自得とも言えそうですが、兄擬(もど)きの泥人形に絶命した彼女はあまりにも不遇に思えます。
とは言え、この重々しさは、後宮に身を置く寿雪、身を置かせる高峻の人生訓とも受け取れそうな気がします。
封宵月(ほう・しょうげつ)の語りによると、寿雪が先代の烏妃から聞き及んだ二人の王の伝承は、どうやら歴史をあまねく語るものではなかったようです。
それに、かつて寿雪が世界地図に驚き、表情に陰りを浮かべていたのは、"梟" なる使者が、烏妃を殺しに来るという伝聞が、確信へと変わったからでしょう。
まず感じたのは、思慕や嫉妬を動機とする二人の王の謂われさえも、初代烏妃の恣意的なフィクションで出来上がっていたらしいこと。
そして、生きた人間に神懸りすることを禁忌とする戒律に触れた妹(烏=烏漣娘娘)を解放するという兄の言い分。
また、その一方で、不可侵を押し通し、隠し通した香薔(こうしょう:初代烏妃)の末裔(=寿雪)を屠(ほふ)るという兄の言い分。
そんな別次元の摂理だったり、無理すじな道理だったりが 、"兄ルート" として伏されてあったとは驚くほかありません。
寿雪と高峻とが紆余曲折してきた最終局面で、予期もしえなかった波乱の展開。
これは、OPのとおりの "ミステリアス" ・・・。
でも、作劇としては、ちょっと "腹立ち" を感じるところもあるんです。
兄ってそんなに強い立場なの・・・?
一つのあぶくから分かれているんだから、弟なのかも知れないのに・・・。
~ ~ ~
「烏妃が望めば何でも叶う」とは、いかにも思わせぶりなセリフに聴こえます。
つまるところ、烏(=烏漣娘娘)が求めた自由奔放への憧れと、香薔(こうしょう:初代烏妃)の相思相愛を願うロマンスとは、謂わば利害の一致するアドレナリンを燃料とする相身互いです。
烏も人間も、それぞれの世界に生きるルールに縛られていますが、もっと違う世界を見てみたい、その世界を大切にしたいという心情は共通するものなのかもしれません。
であれば、この物語は、世界の境界線を跳び越え、類さえも超えて自己実現を追い求める、魂の理想する生き方を描こうとしているとも類推できそうです。
ですが、分を超えた見返りはあまりにも大きく、歴代の烏妃はその一生涯を後宮からは出ることを禁じられ、烏漣娘娘もまた新月の夜以外は後宮からは出られないという足枷を負ったのは皮肉な設定です。
烏妃のアイデンティティーは二重複相性(烏は烏漣娘娘、妃は巫女)です。
宵月によれば、寿雪が献上していた牡丹の花は、妹に「毒」を食らわせていたとの評定です。
烏と人間の同位体など、どんなに共存を図ろうとしても、もとから歪(いびつ)を抱えたものであり、無理くりバランスを取ろうとするための麻薬だというのです。
香薔(こうしょう:初代烏妃)と烏(=妹、烏漣娘娘)とに、どのような契約があったかは窺い知れません。
でも、それぞれの思いには "ならぬ道、なしたき夢" があったのではないかと感じます。
ですが、両者の振る舞いが千年に至るとなれば、妹の苦しみはすでに破綻を迎えているとも宵月は言い放ちます。
寿雪にしてみれば、たまたまその器として見出されただけのこと。
新月に痛みを受け入れる理由などどこにもないし、烏と一蓮托生に生きる責任なども1ミリもありません。
ならば、現役の冬の王、夏の王は、何をどのようにして世界の辻褄を合わせればいいのでしょう。
~ ~ ~
高峻にとっては、帝国の興隆と安泰は、寿雪個人の人生を犠牲にバーターされたものです。
その初発は、いにしえの女性の勝手や古き皇帝の都合であり、謂わば、世界のしがらみを自ら生み出した我利我欲とも言えるわけです。
宵月にとってもそれは同じで、妹を苦しめる一番の理由が烏妃の存在であるという主張ですので、千年の忍従を解き放つには器たる寿雪を殺さねばなりません。
寿雪を守りたい高峻と、屠りたい宵月。
人間の世界線と、鳥の名を持つ者のそれとが、それぞれに譲れぬ価値観をぶつけ合うせめぎ合い。
これは・・・すでに寿雪一人がどうのこうのできる問題ではなさそうです。
宵月と高峻は、いったい寿雪をどうするつもりなのでしょう。
そして、烏(=妹=烏漣娘娘)は、彼らに何を訴えるつもりなのでしょう。
次回は、「想夫香(そうふこう)」です。
なかなかに楽しみです。
{/netabare}
13話。
{netabare}
烏(からす)には、特別な役職名があって、死者の魂を先導する "ミサキベ" とのことです。
文字を当てるなら、おそらく「御先部」でしょう。(原作は「岬部」と表記)。
今回のお話のテーマは "想夫香" です。
後宮のしきたりによれば、亡き人へ心を馳せながら、懐かしさを悼み、愛おしさに慈しみを深めるという意味のようです。
それなら、たとえば、別離やすれ違いなどで心が通わなくなり、後悔に苛まれるときにはどうでしょう。
あるいは、叶わぬ再会に希望を失いかけ、やり切れなさに胸が潰れそうなときにはいかがでしょう。
そんな我流や今様にも "ミサキベ" の名を当てたり "想夫香" を求めてもいいものでしょうか。
とは言え、そんな情けめいたことに耽ったり、試したりする人はもうわずかでしょう。
むしろ、女々しすぎると、揶揄されたり、訝しく遠ざけられたりされるかもしれません。
ただ、寿雪が牡丹を献上するときの表情に、私は彼女の愁いと苛立ちを感じてしまうのです。
香を焚くのなら、それなりの理由や背景があって然るべきことを寿雪は知っています。
それなのに、その謂れさえも聞かされていないのでは、なぜ後宮に独り縛られねばならないものかと、気分は塞ぐばかりでしょう。
7話に「忌々しい烏漣娘娘の見張り役め!」とシンシンにすごむ寿雪がいましたが、私もついつい頷くのです。
「梟が私を殺しに来た。」と淡々と話していた寿雪です。
そんな諦観や、死をも覚悟するような彼女は、心中では、わびしさや失望感に喘いでいたのかもしれませんね。
~ ~ ~
封宵月(ほう・しょうげつ)は、牡丹の香りは "毒"を以って妹を縛る禁忌の手合いだと言います。
でも、千年の軛(くびき)を超えてまで、双子の妹の命を消そうとする振る舞いが、いったいどうして "想夫香" に相応しいというのでしょう。
なぜなら、宵月は、寿雪に "自身の倒し方" さえ教えているのですから。
そう思うと "想夫香" の本当の意味が分かろうというものです。
薛魚泳(せつぎょえい=冬官)であれば、麗娘(れいじょう=先代の烏妃)への懐古をたどることに。
寿雪であるなら、高峻との未来を、二人の王、唯一の友として紡いでいくことへ。
宵月(=梟)なら、自らも禁を冒し、高峻に爪を残してでも、妹(=烏)との再会を果たしたいことを。
そして、妹もまた "自分自身に還る日" を待ち焦がれていることを。
~ ~ ~
物語は放送を終わりましたが、続きを予感させるシーンも配されてありました。
後宮を離れ、夜空を翔ける寿雪の姿は、きっと "歓喜する烏の魂" を示しているのでしょう。
墨をすっかり落とした髪は、烏漣娘娘のま白き頭を象徴しているのでしょう。
彼女に呼び掛ける声は、幽宮(かくれのみや)にいた頃の "兄妹" の姿なのか、あるいは "父母" なのかと、想像が膨らみます。
そう思うと、鳥に化身する人も、寿雪や高峻たちにも、"魂は美しいもの" と扱う心は同じ価値のように感じます。
もしかしたら、原作には、二つの世界をつなぐシナリオと、それぞれの時間を切り結ぶストーリーが記されているとでもいうのでしょうか。
であるなら、放送の続きを期待しながらしながらも、ついページを繰ってみたい気持ちにもなっています。
~ ~ ~
おまけ。
{netabare}
日本には「香道」と呼ばれる芸道があります。
その香りは、あまりに微かであり仄かに過ぎるため、ほかの匂いが混じることを避けるのはもちろん、風に流されてしまうことも厭われるため、静かでほの明るい部屋(香室・こうしつ)で嗜まれます。
特徴的なのは、香りを "かぐ" のではなく、"聞く" というお作法(聞香・もんこう)です。
そんなしきたりを通じて、いつかどこかの感情を探し、見えない言葉を手繰り、ようやく文字に紡いでいく奥ゆかしさが、とても古風に思われますし、雅な雰囲気があるような気がします。
タイミングよく、今ころは "寒牡丹" のシーズンです。
わらの霜囲いに守られて咲いている様子は、寿雪が夜明宮に沈思黙考するイメージにぴったり。
しがらみに囲まれて寒さに耐え忍ぶ姿は、むしろ健気と思われ、艶やかな華とも感じられます。
ところで、寒さのなかで花を愛でるのは、心には風流ですが、身体にはかなり凍(しば)れるものです。
もしも、その香りを嗅ぎ、声を聞くのでしたら、きっと "春牡丹" がふさわしいでしょう。
桜の散り落ちたあと、藤の房のふくらみと合わせ、牡丹の大輪を手に取っていただき、ついでにお団子などを頬張るのが、寿雪のように楽しめるというものでしょうね。
そんな春を待ち遠しく思います。
{/netabare}
{/netabare}
23