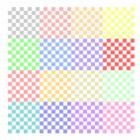hiroshi5 さんの感想・評価
4.3
物語 : 4.5
作画 : 4.0
声優 : 4.0
音楽 : 4.0
キャラ : 5.0
状態:観終わった
今まで謎だった疑問がやっと解けた!!!閃きってこういうことを言うのねw
今回は一期とはまったく違った視点からこの「オオカミと香辛料II」レビューを書こうと思う。
二期のホロの破壊力は凄まじいの一言だった。そのあまりの可愛さ故に、本編中、ホロが悲しい顔をすればこちらも悲しい気分になるというくらいだ。
その可愛さの根源は私は尻尾と耳にあると私は考える。可愛いキャラなら他にも一杯いる。ちなみに、私はあずにゃんとシャルルが大好きだ。しかし、このホロというキャラはその二人に勝るとも劣らない可愛さを誇っていた。
ホロの顔は勿論可愛い。特にその赤い瞳は破壊力満点といったところだろうか。しかし、ホロの最大の強みは前述した尻尾と耳だ。動物愛とでも言うのだろうか。表情だけでは表すことができない内面を尻尾と耳は表現することができる。
言葉は嘘をつけても体は嘘をつけない(何か表現がエロチックだがw)とはよく言ったものである。本当に尻尾と耳は喜怒哀楽を表現するのに適している。しかも、そのリアルな動きはある意味アニメーションを通してしか再現することができないといっても良いだろう。
ということで、ホロの可愛さの本質に触れたところで、本題である。
私は本編を見ていてふと疑問に思った。ホロに感情移入しているが、ホロがクラフトを結ばれることになって素直に嬉しいと思った。これはおかしくないだろうか?
自分の好きなものにはある程度「独占欲」があるものだ。なのに、ホロがクラフトと良い関係になれば成る程見ている私は良い気分になった。
これは他のアニメでも同じだ。「生徒会長はメイド様」や「とらド
ラ!」ども女性キャラに対して本物の愛情といっても良いほどの想いを抱いているのに、他の男性キャラと仲が良くなることに幸せを感じる。
一体どんな感情システムが作用すれば自分の女が他者と一緒になることに対して嬉しく思うのか、これを今レビューのお題にしたい。
この現象を簡単に表記する為に{netabare}「非現実性の愛情」{/netabare}と名づけよう。
と言っても、感情論や精神面に関する知識は塵ほどもないので、色々な本や記事を参考にして纏めていきたい。
まず、自分の仮説としては作品の視点が大きく関係しているのでは?と思っている。第三者の視点から作品を描く、この事実が視聴者の無意識下で「虚構」と「現実」の壁を作っているのではないだろうか。
これはリアルではない、と思い込むことで、その作品の流れに対して客観視が可能になる。客観視=自分には直接的な関係はないと判断することに繫がる。
しかし、自分で仮説を立てて置いてなんだが、これは矛盾は孕んでいる。「感情移入」とは他人のことを自分のことの様に感じるという意味だ。客観視とは相違の立場にある。
では、感情移入しながら、その作品をアンリアルだと割り切るものとは何だろうか?
実写ではないからか?
物語はあまりに現実とかけ離れているからか?
どちらも違うだろう。ドラマでも同じ現象は起こるだろうし、ドラマは現実的物語を売りとしている部分がある。
今考えれば、「非現実性の愛情」は媒体の中でどこにでも生じる現象だ。アニメ、ドラマ、本、演劇。どこにもキャラクターが存在し、その作品内の愛情に関しては感情移入しつつも、どこか現実とは割り切って鑑賞している。これが大衆の現実だ。
そこで、一つ社会学の考え方をお借りしたい。(ここからはアニメに関係ない話なので飛ばしても可)
{netabare}「人間は本質的に利他的な存在だ」。こんな近代資本主義社会に反する説がある。利他的、即ち他者に利益になることをする(善行)ことで自分も幸せになる、というものだ。資本主義は市場の自由競争を許すことで、弱肉強食の世界を作り強者が弱者を支配する仕組みになっている。そこに社会と法律という画期的な発明によって富裕層が持つ富の分配を可能にする。ここから「平等」だとか「人権」みたいな言葉も生まれてくるが、そもそものこれらの単語は「自由」な競争の保証の為にある単語である。
資本主義と聞くと、アメリカを思い浮かべる人も多いだろう。まさに1950年代のアメリカは真の資本主義だった。アメリカンドリームという言葉を聞いた事があるだろうか?アメリカンドリームとは誰でも成功するチャンスがあり、誰でも当時理想とされた生活(一軒家を持って、車を持って、テレビを持って、大きな庭を持つなど)を手にい入れることができるという意味だ。
事実、当時のアメリカはそうだった。しかし、振り返ってみるとそのアメリカンドリームは「利己的姿勢」を貫き通した結果であったといっても良い。
自分の成功がアメリカ市場向上になると信じ込み、仕事を有限な資源を考慮せずひたすら「成功」を追いかける。
日本も勿論その資本主義を取り入れた。利己的姿勢こそ総合的な幸せに繫がると信じてきた。現代の日本人もそう思っている人が大多数だろう。しかし、歴史をちょっと学べばそれが間違いだということがすぐ分かる。その理由をこれ以上詳しく説明すると話がどんどん逸れてしまうので省略するが、簡単にいえば利益を追い求め続けると効率性や利便性だけを追求してしまい、どんどんシステム化される。システムが大規模化すると社会という構成上どうしても権益を独占しようとする傾向が生まれ、現在のアメリカ社会のようなアメリカの富の80%を僅かな大富豪が支配することになってしまう。また、社会システムを過信することになり、「オオカミと香辛料」一期のレビューで述べたような「自然」を考慮しない、緊急時にまったく起動せず、己の首を絞める羽目になる。
さて、「人間は利他的存在」というフレーズが近代資本主義に如何に反しているか理解して頂けただろうか?
しかし、社会学はこれからの社会システム論を考えた時に「利他性」こそ重要になると言っている。「共生」、これがもっとも重要な単語だ。一時期話題になっていた道州制度なるものも、現在必死に重要性が強調されている「参加と自治」の概念もこれに既存する。
それは民衆が権力を監視するという意味で権力の暴走を止め、健全な社会を確立するという面で合理的なシステムだ。
つまり、「利他的精神が人間の本来の精神に通じる」というのは至極納得のいく説明なのだ。利他的精神を呼び覚ます、その潜在的性質をメディアは持っているということだ。{/netabare}
長々と書いてきたが、要するにこうだ。近代資本主義が今まで推し進めてきた「利己的精神」に対極的な「利他的精神」は人間の本質を示すもので、アニメなどの媒体はそれを呼び起こすということだ。
さらに、補充としてちょっと書いておこう。我々がアニメ作品を視聴する時、何を求めて見るのか。
多分、ごちゃごちゃ理由はあるかもしれないが、根源的な理由は「楽しめるか否か」ではないか?
作品の楽しみ方は様々だが、可愛いキャラを愛でるのも勿論一つの楽しみ方だろう。つまり、視聴者は作品を見る時点で何かしら現実と作品を割り切っている。
■現時点での結論として以下のようになる。
{netabare}正直分からんw{/netabare}
ただ、理解しているのは
・作品を見る、見ないの時点で「非現実性の愛情」は生じている。
・キャラに感情移入して「ホロが幸せになって欲しい!」と人間の潜在的な利他的精神が何らかの理由によって即発される。
・しかし、キャラの感情移入しきることはなく、どこかで境界線が引かれている。
という風にここまで書いていて、決定的な点に気付いた。
以前何かの記事で読んだ内容だ。「感情移入と他者理解は違う」だったと思う。
「非現実性の愛情」を解決するのはこれに限るだろう。
感情移入とは一方通行だ。別の言い方をすれば、一方的な共感だ。「あ~、ホロの気持ち、凄いわかるわ~」と言っても、本当のホロがそう感じているのかは視聴者に確かめる術は無い。
ここが、現実と虚構の境界線だろう。応答能力、とでも言うのだろうか、他者理解をする為には相手の返答が必要になる。
この違いを我々視聴者は無意識に理解しているのだ!!
考えて見て欲しい。もし、貴方の好きなキャラクターが応答能力を持っていたとすると・・・
自分「ホロ~、君はやっぱり可愛いよ。」
ホロ「言わんでも分かっとる。わっちは賢狼ホロじゃ!」
これは第三者の視点なんかではない。主観そのものだ。多分、こんなことが可能になってしまえば、きっとオタクの数は今の1000倍は増えることだろう。ということは、感情移入は客観性そのものではないか!
最初に記述した仮説を矛盾だと証した説明文こそ、間違いだったということかw
■結論
{netabare}
アニメという一方的な媒体が我々に「他者理解」ならぬ「感情移入」をさせ、「現実」と「虚構」の境界線を引き、「非現実性の愛情」を醸しだすのだ!!!
作品が「楽しいか否か」で決めるのも「感情移入」できるか否かに大きく関係していると思う。
そして、もう一つ重要な点は
「感情移入」は「客観的」であり、「他者理解」こそ「主観的」だということだ。
{/netabare}
いや~、今まで一番しっくりくるレビューが書けました^^